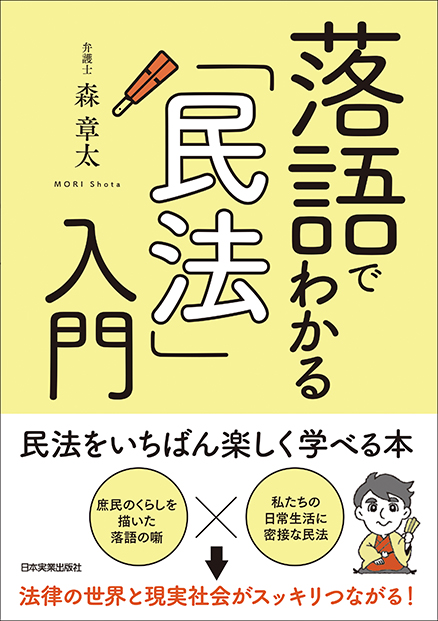自分らしい人生の最期を迎えるための準備=終活(しゅうかつ)。身辺整理をするなかで、家族への遺産分割に頭を悩ませるのは、いつの時代も同じようで……。江戸の商人・赤螺屋吝兵衛(あかにしやけちべえ)も、3人の息子のうち、だれに家督を譲るか決めかねていました。はたして、迷った末の結論は……。古典落語『片棒』を題材に、「相続する人・される人」が知っておきたい「遺言」制度についてお話ししましょう。
※本稿は『落語でわかる「民法」入門』(弁護士:森 章太・著)をもとに一部抜粋・再編集しています。
あらすじ:『片棒』
〈麻生芳伸 編『落語特選 下』(筑摩書房、平成12年)341〜352頁 参照〉
赤螺屋吝兵衛は、食うものも食わず貯め込んで、一代で金持ちになった商人である。3人の息子のうち、だれに家督を譲るか決めるため、自分が死んだらどのような葬式を出すかをそれぞれに尋ねた。
長男の松太郎は「料理代と車代だけで1人当たり30円(勤め人の1か月分の給金相当額)かけ、3000人が出席する豪勢な葬式を行う」という。吝兵衛は「貯めた金が葬式のためになくなってしまう」と嘆く。
次男の竹次郎は「山車(だし)の上に算盤(そろばん)を弾く吝兵衛の人形を設置するなど、祭りのような葬式を行う」と答え、吝兵衛は呆れる。
三男の梅三郎は「葬式を立派に行う必要はない、棺桶(かんおけ)を買うとお金がかかるので、物置にある菜漬の樽で間に合わせる」と答える。しかし、「樽を人足(にんそく※)に担がせると日当を払わなければならないので、自分が片棒を担ぐつもりだが、もう1人の担ぎ手がいない……」という。すると、吝兵衛がいう。
「なあに心配するな、片棒はおれが担ぐ」
※人足……力仕事をする労働者
特定の人に遺産を譲る「遺言」制度
吝兵衛であれば、経費節約のため、いかにも自分の死体が入った樽を担ぐのではないかと思えるところが、落語『片棒』の面白さです。子どもたちが遺産分割で争うようなことがあれば、吝兵衛が黄泉の国から現れて差配するかもしれませんが、現代日本では、特定の人に遺産を譲る方法として「遺言(いごん)」という制度があります。
遺言は、自分の死後に一定の効果を発生させる個人の意思表示で、遺言者(被相続人)が亡くなってはじめて効力が生じます。15歳以上であれば遺言することができますが、基準年齢を超えているからといって、必ずしも効力が認められるわけではありません。高齢者などで意思能力がなく、遺言が無効と判断されることもあります。
他方で、一定の相続人に最低限保証される、遺言によって侵害されない持分的利益=「遺留分(いりゅうぶん)」があります。被相続人が贈与(ぞうよ)および遺贈(いぞう)などによって自分の財産を自由に処分することに対して制限を加えるものです。
もし、吝兵衛が三男に財産をすべて譲るなら、遺言書を作成するのも1つの手段ですが、その場合、長男と次男は遺留分を侵害されることになります。では、どうすればよいのでしょうか。ここでは、わかりやすくするため、吝兵衛の(推定)相続人は「子3人のみ」であることを前提に話を進めていきましょう。
※明治31年に施行された民法には、家督相続(戸主の地位の相続)と遺産相続がありましたが、昭和23年に施行された改正民法において家督相続は廃止されました。
自筆証書遺言の作成ルールは厳格
遺言の方式のうち、よく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言とは、遺言者が「遺言書の全文」「日付(作成年月日)」および「氏名」を自分で書き、「押印」して作成する方式です。遺言の効力が生じるときには遺言者が生存しておらず、遺言者の真意を確認できないため、遺言の作成ルールは厳格になっています。
遺言者は、本人が作成したことがわかるよう、全文を自分で書かなければなりません(財産目録についてはワープロ打ちでもよい)。日付が必要とされる理由は、 遺言能力の存否や複数ある場合における遺言書作成の「先後」を判断するためです。
自筆証書遺言の押印は、実印である必要はなく、認印や指印でもかまいません。また、遺言内容の変更や加除を行うときは、遺言者が変更・加除した旨を付記して署名し、その変更場所にも押印が必要です(単なる誤記の訂正には不要)。近年は書類の電子化が進み、日本のハンコ文化も変容しつつありますが、重要な文書については作成者が署名後に押印することで文書の作成を完結させる慣行が根強く残っています。
自筆証書遺言の長所は、作成費用があまりかからないこと。いかにも『片棒』の吝兵衛が重視しそうな点です。一方、短所は、作成ルールが守られていないために遺言が無効とされたり、遺言書が隠匿などされるおそれがあるということ。さらには、遺言者の死亡後に家庭裁判所による「検認(けんにん=偽造・変造を防ぐために原状保全する手続き)」が必要であり、遺言能力をめぐって争いになりやすい面もあります。
自筆証書遺言の「検認」は遅滞なく…
遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく、検認の請求をしなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で開封しなければならず、検認を経ないで遺言を執行したり、裁判所外で開封したりした場合は、5万円以下の過料になります。もっとも、家庭裁判所外で開封したからといって、遺言が無効になるわけではありません。
検認の請求がされると、家庭裁判所は、検認期日を定め、相続人に呼出状を送ります。検認期日では、出席した相続人などの立会いのもと、裁判官が(封印のある遺言書の場合は)開封したうえで遺言書を検認します。検認後、検認済みの証印を付した遺言書は、申立人(保管者)に返還されます。検認期日に欠席しても、後日、家庭裁判所で検認調書と遺言書写しを謄写することができます。
この検認によって、遺言書の形状、加除訂正の状態など検認の日現在における遺言書の内容を明確にできますが、検認を受けたからといって、その遺言が有効であると裁判所が認めたことにはなりません。
なお、2020(令和2)年7月から、法務局(遺言書保管所)に自筆の遺言書の保管を任せることができるようになりました。保管申請費用は1件につき3900円。法務局で保管されている遺言書は検認が不要です。
公証人が作成する公正証書遺言
一方、公正証書遺言は、遺言者から遺言の趣旨を伝えられた公証人が筆記して公正証書によって作成する方式です。公証人というのは、実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
公正証書遺言の作成方式は民法に定められていますが、実際には、遺言者(またはその代理人)から遺言の内容を事前に聴取した公証人があらかじめ証書を作成し、これを遺言者に読み聞かせ、遺言者がこれを承認するかたちで 「口授(こうじゅ)」を行ったこととし、署名および実印による捺印をして完成させることも多いようです。
作成場所は、原則として公証役場です。ただし、遺言者が病気や高齢などのために公証役場に赴くことができない場合には、病院や自宅などで作成することもできます。
公正証書遺言の長所としては、公証人が関与し、公証役場に原本が保管されるので(正本・謄本は遺言者等が保管)、形式不備から遺言が無効となったり、偽造などのおそれが小さいことが挙げられます。自筆証書遺言に欠かせない検認も不要です。
一方、短所は、公証人手数料の支払いと2人以上の証人が必要になること。また、公正証書遺言であっても、遺言者に遺言能力がなかったことにより、遺言が無効になることがあります。もし『片棒』の吝兵衛が公正証書遺言を作成するなら、「自分が証人にもなる」といいそうですが、遺言者本人は証人になれません。また、推定相続人も利害関係者なので証人にはなれないため、吝兵衛の子も証人にはなれません。
財産を無償で譲る「遺贈」
遺言者が遺言によって財産を与える「遺贈(いぞう)」は、相続人以外の第三者に対して行うこともできます。「特定遺贈」と「包括遺贈」があり、特定遺贈とは、特定の財産を与える遺贈のことで、権利のみが与えられます。包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合を与える遺贈で、権利のみではなく、義務(負債)も承継されます。
相続人に対して遺贈することもできますが、特定の相続人に遺産の全部を相続させるという内容の遺言は包括遺贈ではなく、(相続分の指定を含む)遺産分割方法の指定です。
また、特定の相続人に特定の遺産を相続させるという内容の遺言(特定財産承継遺言)は特定遺贈ではなく、(相続分の指定を含む)遺産分割方法の指定であり、遺産分割手続きを要することなく、被相続人の死亡時に直ちに相続により承継されます。
遺言により指定された財産の取得を望まない場合、特定遺贈であれば、遺贈を放棄したうえで他の遺産を相続することができます。しかし、 特定財産承継遺言のときは、相続なので指定された財産のみを放棄することはできず、相続放棄をしない限りは指定された財産を取得することになります。
【もし、受遺者および承継者が亡くなったら…】
遺言者が死亡する以前に遺贈を受ける者(受遺者)が死亡したときは、遺贈は無効になります。また、特定財産承継遺言の場合も、遺言者が死亡する以前に承継者が死亡したときは、原則として無効となります。代襲して受遺者などの子が遺贈などを受けることができるわけではありません。
なお、被相続人が死亡する以前に相続人となるべき者が死亡していたときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限る)が代襲して相続人になります。
もし、『片棒』の吝兵衛が三男に対して遺贈するまたは相続させる旨の遺言を作成した場合、吝兵衛の死亡以前に三男が死亡したときは、遺贈などは無効になります。三男の代わりに三男の子(吝兵衛の孫)が代襲して相続人にはなりますが、遺贈などを受けられるわけではありません。三男が死亡した場合には三男の子に取得させる考えがあるならば、その旨を遺言書に明記などすることが必要です。
「遺留分」を請求する権利
冒頭でもふれたとおり、被相続人の財産の中で、一定の相続人に留保されている持分的利益を「遺留分」といいます。被相続人が贈与および遺贈などによって自分の財産を自由に処分することに対して制限を加えるものです。
遺留分権利者となるのは、相続人(兄弟姉妹を除く)です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は「3分の1×法定相続分」、それ以外の場合は「2分の1×法定相続分」。遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、受遺者または贈与を受けた者に対して金銭債権を取得し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
たとえば、『片棒』の場合、長男の松太郎、次男の竹次郎、三男の梅三郎の遺留分はそれぞれ6分の1(=3分の1×2分の1)。もし、吝兵衛が三男に財産をすべて譲るという遺言をしたなら、長男と次男はそれぞれ、三男に対して、財産の価額の6分の1に相当する金銭の支払いを求めることができるわけです。
なお、侵害額を請求するかどうかは、遺留分権利者の自由ですが、遺留分侵害請求権は、相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから「1年間」行使しないと、時効によって消滅します。また、相続開始時から「10年」を経過したときも消滅します。
「遺言」は変更・撤回できる
遺言を作成したものの、後で状況が変わったり、内容を見直したいこともあるでしょう。遺言には契約のような拘束力はないので、遺言者は遺言をいつでも変更・撤回することができます。
撤回する場合、遺言書にその旨を明記する必要はなく、前の遺言書と抵触する内容の遺言書を作成すれば、 撤回したことになります。また、撤回は同一の方式である必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
たとえば、『片棒』の吝兵衛が、仮に次男と三男に2分の1ずつ譲るという内容に変更したいのであれば、その旨を記載した遺言書を作成すればよく、「前の遺言を撤回する」とあえて記載する必要はありません。
このほか、後のトラブルを避けるため、遺言書は遺留分を考慮した内容にしたり、遺言事項(法定された遺言でなしうる行為)ではないものの、付言事項として遺言書の内容とする理由を記載することも多いようです。
*本記事の内容は、2020年10月現在の法律に基づいています。
著者プロフィール:森 章太(もり しょうた)
弁護士。1981年生まれ。横浜市立大学商学部経済学科卒業。税理士法人勤務、税理士試験合格。慶應義塾大学大学院法務研究科卒業。司法試験合格後、弁護士登録。東京中央総合法律事務所所属。横浜市立大学での市民向け講座の講師並びに税理士団体及び企業での研修講師を務めている。