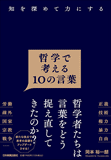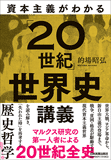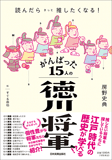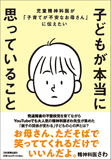川を知る事典 日本の川・世界の川
| 発売日 | 2003.10.22 |
|---|---|
| 著者 | 鈴木理生 |
| 判型 | 四六判/並製 |
| ページ数 | 312 |
| ISBN | 978-4-534-03656-8 |
| 価格 | ¥1,760(税込) |
北海道に始まりアフリカに終わる日本と世界の川を紹介しながら、川と人間の関わり方、、自然河川と運河、古今東西の川の意識の変遷などを、豊富な蘊蓄とともに書き記した一冊。事典としても人文書としても面白く読める、都市史研究第一人者による渾身の書。
≪章立て≫
第1章 「川」のつく地名
第2章 川とは何か
第3章 日本人の川への意識
第4章 人工水路と運河
第5章 地球上の川とガワ
第6章 世界の運河と川
オンラインストアで購入する
テキスト採用など、大量・一括購入に関するご質問・ご注文は、弊社営業部(TEL:03-3268-5161)までお問い合わせください。
詳細
第1章 「川」のつく地名
1 「カワ」という表現 12
日本の「川」と外国の「カワ」 12
漢字文化圏の「川」の表現 13
2 北海道の川と名前 16
地名に残る「ナイ」と「ベツ」 16
函館から渡島半島~石狩湾まで 18
「日本一の大河」は? 20
<補>河川短縮工事のツケ 21
稚内近辺から網走まで 23
知床~襟裳岬、そして函館まで 24
北方領土では 26
<附>新領土北海道 27
3 東北地方の川と名前 32
地名に残る土地の記憶 32
青森~岩手県に見る「辺」「戸」とその由来 34
<附>田村麻呂の謎 36
岩手県に見る「ナイ」と「ウチ」 41
日本海文化圏の中心的な湊を持つ秋田県 42
秋田県に残る「別」と「内」 43
4 中国~朝鮮の「川」「河」「江」 47
黄河の「河」と長江の「江」 47
中国東北地方と四川地方 50
朝鮮半島の場合 51
<補>日本の「河」と「江」と「川」(セン) 54
第2章 川とは何か
1 「かわ」と「がわ」の意味するもの 58
日本特有の「川」の命名法 58
無数の滴りが「沢」をなす 60
沢・瀬の呼び方 62
<附>血筋の表現 64
「川」の変形──池・沼・湖 66
<補>琵琶湖と世界の湖 67
2 川は側(ガワ)をつくって流れる 70
一滴の雨から谷までの流れ 70
<附>シミズ・キヨミズ・セミド… 72
「ガワ」(岸辺)の風景 74
植生を巡る流れと沙漠を流れる川 75
<補>「南水北調」 77
氷となっても流れる 79
3 井戸というカワ 80
井戸のタテ・ヨコ 80
ヨコ井戸文化圏 81
<補>江戸のカナート 83
天井(てんじょう)ではない天井(てんせい) 85
4 近代日本の川 87
明治政府の川の定義 87
河川の流長と幹支流航路 89
蛇行現象の実例──セーヌ川・ティグリス川と利根川 92
<附>「たゆたえども沈まず」 96
第3章 日本人の川への意識
1 水の上下という感覚 98
『記・紀』より受け継がれた「三尺流れれば清し」 98
水の「良・悪」と「上・下」 99
川の稀釈能力 101
都市施設としての上下水道 102
ポンプ利用で変えられた河川の姿 105
<附>かわや=川屋 108
「ガワ」を否定した都市河川行政 110
<補>道にみる「カワ」と「ガワ」の意識 112
2 古典で見た川 114
万葉人の見た「天の川」 114
「百人一首」に流れる川 116
蕪村の見た川 121
<附>その他の蕪村の詠んだ川 127
3 江戸期の谷間の表現 130
最初の有料トンネル? 130
広がる耶馬渓・増える「渓・峡」 132
北海道から関東までの「渓・峡」 133
中部・近畿地方では 135
西南日本の場合 136
養老の滝 138
4 旧国名と川の役割 140
古代の国とその並び方 140
<附>国の異名・異称 143
畿内を流れる川と国──摂津・和泉・河内 144
京都と日本海を結ぶ要所──近江 148
<補>淀川水系の源は? 149
三河国とアズミ族 150
<補>川を遡った種族 154
遠江国と駿河国 155
5 アラカワと「カワ」のつく地名 158
地名としてのアラカワ 158
東京を流れる「荒川」の変遷 160
上杉ゆかり、新潟県の2つの荒川 162
「何々カワ」と読ませる地名 164
<補>東京に意外に多い「カワ」 167
川のつく県にはその名の川はない? 168
名は態を表す「新潟」 172
信濃川・阿賀野川とその地域開発 175
<附>新潟湊の繁栄 178
第4章 人工水路と運河
1 人工水路と日本人 182
川と人間の最初の関わり 182
灌漑とは人工湿地づくりのこと 183
玉川上水も荒川も「川」 185
狂心(たぶれごころ)の渠(みぞ) 186
万葉集に見る明日香川二態 188
石の都は水の都 189
<補>飛鳥時代にロック式水路はあったか? 190
2 琵琶湖疏水 192
1兆円以上?の大事業 192
「哲学の道」沿いを流れる水の向きは? 195
二条大橋付近と高瀬川 196
<補>運河と海上交通の整備 198
工事の結果としての新しい施設 199
疏水の最末端──伏見 200
かつての巨大湖──巨椋池 202
<附>揮毫に見る工事関係者の「器」 204
3 歴史的な世界三大運河 206
遣隋使の時代から今も使われる中国の大運河 206
黄河と長江の水位差(ロック式のしくみ) 209
観光地ベネチアとヴェルサイユ宮殿の運河 212
<附>長城の煉瓦に見るもう1つの「水運」 215
第5章 地球上の川とガワ
1 「世界の屋根」から流れる川 218
地球の2つの大造山帯 218
アジアの文明を築いた大河の源 219
北極海を目指す川 224
北極海の汚染 226
<附>大学入試センターの試験問題図 228
2 アジア西端と地中海沿岸 230
蜜と乳が流れ、石油の富をもたらす川 230
よく流れる川「ヨルダン」の水不足 233
3 森林と川 236
レバノンの国旗 236
<附>森林の加工用具 238
多摩川流域の自然回復 239
<附>咢堂・尾崎行雄 240
武蔵野現象 242
第6章 世界の運河と川
1 近代は運河時代に始まる 246
西欧(オクシデント)と東洋(オリエント)の境目──スエズ運河 246
人造湖によってロック式が可能に──パナマ運河 247
海にある運河──沿海運河 250
2 運河ランド・ヨーロッパ 255
一体となっている自然河川と運河 255
馬車による標準的な運搬重量 257
ロシア中央高原の川 259
<補>バトンタッチ方式だった曳舟 263
黒海に流れ込む川 264
黒海の役割とビザンチン帝国 265
<附>「側」を残すイスタンブールの歴史遺産 267
ライン川を中心にした運河網 270
ライン河口~フランスの水路 271
実用性を優先したイギリスの内陸水路 275
<附>やはり「川」「流れ」が川の名前の由来 277
3 水運王国・アメリカ 278
川に“倉庫”が航行する──アメリカの「M・R・S」 278
2つのNを結ぶ水路 280
「発見者」の名簿のようなカナダの川 283
<附>「一衣帯水」の湖沼地帯と豊富な地下資源 286
先住民の言葉づくしの新世界・アメリカ 288
4 アフリカの自然河川 291
青ナイルと白ナイル 291
政治的な川・湖の名 292
歴史の影響を大きく受けるアフリカの地名 293
ザンベジ=〈大きな川〉 296
ザイール=〈力強い川〉 297
ニジェール=〈川の中の川〉 298
<附>ハゲても「輝く山」か 301
おわりに なぜアフリカで結んだのか
○川を見る2つの視線 302
○ヒトゲノム解読 305
○「ガワ」の十字路 306
著者プロフィール
鈴木理生
1926年東京生まれ。1986年まで千代田図書館勤務。都市史研究家。著書に『千代田区の歴史』(名著出版)、『江戸はこうして造られた』(ちくま学芸文庫)、『東京の地理がわかる事典』(日本実業出版社)、『江戸の橋』(三省堂)などがある。