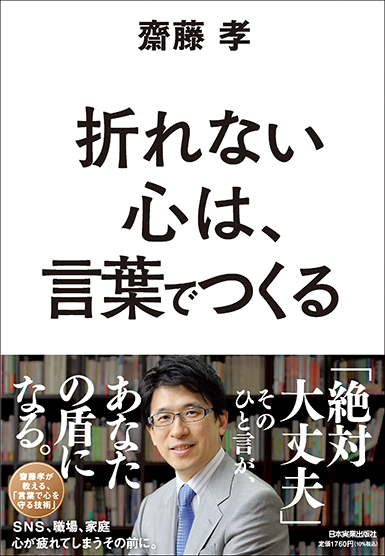「いいね」の数やランキングが影響力を持ち、誰もが誰かから「査定」されているように感じる現代社会では、必要以上に他人の評価を気にしたり、自分を否定したりするネガティブな感情に陥りがちです。数々のベストセラーで知られる齋藤孝氏は、そんな中で自分の心を守るために「他人に左右されない自分の軸を育てよう」と説きます。
※本稿は齋藤孝『折れない心は、言葉でつくる』の一部を抜粋したものです。
自分だけは、絶対に自分の味方でいる
「自分は自分の味方」。この言葉を私は小学生の頃から心に刻んできました。どんなときでも、自分が自分の敵になることはしないという強い意志が、心の安全基地になります。自分の中に「もうひとりの自分」がいて、そっと支えてくれるような感覚です。
失敗しても、自分を責めすぎない。反省はしても、否定はしない。そんなふうに自分を扱うことで、世界中が敵に回ったとしても「自分は大丈夫」と思えるようになります。
孟子の言葉にあるように、「自ら顧(かえり)みてなおくんば、千万人といえども我行かん」。この精神を支えるのは、結局「自分は自分の味方だ」という確信なのです。
「勝ち負け」に振り回されない心の持ち方
「自分を信じれば勝てる」と言ってしまうと、勝てなかったときに自分を信じられなくなる危うさがあります。勝っても負けても、自分を信じる。それが本物の自己肯定力です。
自己肯定感は「結果」ではなく「存在」に宿ります。試験に落ちた、仕事で失敗した、誰かに否定された――「それでも自分は存在しているし、ここにいる」という感覚。これこそが揺るがない安心感を生む源なのです。
自己肯定感は「才能」ではなく「技術」
自己肯定感は、努力で身につけられる「技術」です。
自転車に乗れるようになることが技であるように、一度身につけてしまえば一生もの。
ポイントは、自分の中に「誰にも傷つけられない中心」を持つことです。これが、最も強い心の技術です。
評価や査定が飛び交う今の社会では、才能や成果で人を判断しがちです。けれども、自分の「存在」そのものを受け入れられれば、誰にも左右されない「自分の軸」が育ちます。そうしてはじめて、他人の目から自分を解放することができます。
査定社会から距離をとるという選択
今はまさに「査定社会」。SNSでの「いいね」やランキング、レビュー評価……私たちは常に誰かからの点数を気にしながら生きています。しかし、それはあなたの“存在”を評価しているわけではなく、ただの“行動の結果”の評価に過ぎません。
だからこそ、自分の存在を無条件で受け入れる回路をつくることが大切です。私は、エゴサーチを一切しないと決めています。自分がどう思われているかより、「自分がどう思うか」を大事にしたいからです。他人に評価されない自分こそが、本当の自分。その自分に向き合うことで、ようやく人生の主導権を取り戻せるのです。
「本当の自分」は見つけるものではなく、認めるもの
新しい哲学の考え方では、本当の自分なんていない、つまり「本当の」なんていうものはないということになっていて、確かにそうなのかもしれないと思うこともあります。
本当の自分を求めてタマネギをむくみたいにむいていっても、中から本当の自分が出てくるわけがないという言い方は、一定の真理を含んでいるかもしれません。とはいえ、そのような考え方は現実社会においてはあまり役に立たないと思います。
本当の自分なんていないんだと言ったとしても、苦しいときに楽になるわけでもなければ、生活にプラスになるわけでもありません。
それよりも、自分の中に大切な自分がいて、それには確かな存在感があり、自分はここにいていいんだ、自分はこのようにして生きていていいんだということを自分自身で認めるということが思考の回路としては可能であり、自分の精神の安定につながります。
本当の自分があるかないかと言っても目の前の問題の解決にはならないので、本当の自分は揺るぎなくあるものとして考え、認めるという考え方です。
「誰も本当の私をわかってくれない」という思いは、少々幼い感じがします。それは他人に期待しすぎです。
“ 誰にも壊されない場所”を自分の中につくる
全然傷つかない自己、黄金の自己、ダイヤモンドのような自己を持つことができると、安心していろいろなことができるようになります。たとえば子どもがまずいことをしでかしてしまっても、それでも子どもを愛し続ける母親という存在はイメージできるでしょう。
岩崎宏美さんの『聖母(マドンナ)たちのララバイ』(作詞・山川啓介)の歌詞のように、何があってもいつでもずっと自分を見守っているという存在に、自分がなるということです。
そのような思考の回路をつくって、ダイヤモンドのような自分がここに存在するとなれば、ほかの人は一切そこに触れることができないものになります。
“ 存在していい”という感覚が、成長を支えてくれる
植物を見て、そのようなことを感じることもあります。植物には、人間のような意識はありません。自己意識もないと思いますが、植物は自分の中の存在を肯定していると感じることが多々あります。ここに生まれてここで育っていっていいと自分に自信を持って育っている感じ、光を求めて育っていくという生命本来が持つ向上していく性質を感じるのです。
種から芽が出て、双葉になって成長してというように、そのように、成長していく性質というものが生命にはあります。その成長の動きというものが自己肯定感のように感じられるのです。
必ずしも能力的に成長し続けなければいけないということではないのですが、ここにいていいんだ、ここに存在していいんだという、誰に遠慮する必要もないんだという、安らかな自信というものを自らの中に持つという感覚は大切でしょう。
著者プロフィール
齋藤 孝(さいとう・たかし)
1960年、静岡県生まれ。明治大学文学部教授。東京大学法学部卒業。同大学院教育学研究科博士課程等を経て、現職。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。『身体感覚を取り戻す』(NHK出版)で新潮学芸賞受賞。『声に出して読みたい日本語』(草思社)がシリーズ260万部のベストセラーになり日本語ブームをつくる。
『本当の「心の強さ」ってなんだろう?』(誠文堂新光社)、『昭和歌謡界隈の歩き方』(白秋社)、『僕の推しキャラたちの名言・名セリフ』(合同出版)など著書多数。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」総合指導、フジテレビ「全力! 脱力タイムズ」、日本テレビ「ZIP!」など、TVコメンテーターとしても活躍中。