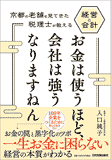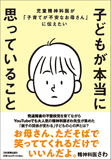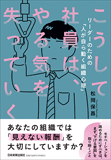ほんとうにわかる棚卸資産会計の実務
| 発売日 | 2008.09.03 |
|---|---|
| 著者 | 松尾絹代 |
| 判型 | A5判/並製 |
| ページ数 | 360 |
| ISBN | 978-4-534-04436-5 |
| 価格 | ¥3,080(税込) |
2008年4月1日以後開始事業年度から新しい「棚卸資産の評価に関する会計基準」が強制適用されます。これまでとどう変わり、どのように評価するかを中心に、中小企業への影響、税務の処理方法まで、具体例やイメージをふんだんに取り入れ、やさしく道案内します。
≪章立て≫
1章 棚卸資産の会計が変わった!
2章 棚卸資産を「保有目的」で分類する
3章 通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価に関する会計
4章 トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価に関する会計
5章 決算書ではどのように開示されるか
6章 適用初年度に注意しなければならないこと
7章 棚卸資産会計に関連するその他の留意事項
8章 中小企業のための棚卸資産会計
9章 法人税法における棚卸資産の会計処理
10章 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正案について
巻末資料
1 棚卸資産の評価に関する会計基準
2 早期適用会社の事例を見てみよう
オンラインストアで購入する
テキスト採用など、大量・一括購入に関するご質問・ご注文は、弊社営業部(TEL:03-3268-5161)までお問い合わせください。
詳細
1章 棚卸資産の会計が変わった!
1 はじめて会計基準ができた理由を知っておこう 18
1 棚卸資産はとても身近な資産 18
2 「棚卸資産」に関する新しい会計基準が公表された 19
3 会計基準のコンバージェンスとは? 19
4 なぜコンバージェンスが必要なのか? 20
5 基準は国際財務報告基準にならって新設された 22
6 これまでの基準と新基準の関係を知っておこう 22
2 棚卸資産は保有目的でふたつに分類して考える 24
1 トレーディング目的で保有する棚卸資産とは 24
2 通常の販売目的で保有する棚卸資産とは 25
3 棚卸資産の分類は会社ごとに異なる 26
3 通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価方法が変わった 27
1 変更の概要を知っておこう 27
2 原価法とは 27
3 低価法とは 28
4 「トレーディング目的で保有する棚卸資産」というはじめての概念 30
1 トレーディング目的の棚卸資産の評価方法がはじめてできた 30
2 会計処理は金融商品の会計基準等も参照する 30
5 通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価損 32
1 計上される区分は売上原価(または製造原価) 32
2 投資家のためにはわかりやすい変更 32
6 新基準はいつから適用するの? 34
1 平成20年4月1日以降開始する事業年度から 34
2章 棚卸資産を「保有目的」で分類する
1 まずは棚卸資産の分類から始める 36
1 端から順番に分類を開始すると時間がかかる 36
2 分類の前に一覧表を作成する 37
3 トレーディング目的の棚卸資産から分類する 41
4 残る資産はまとめて分類する 41
5 分類は経営者の意思として明文化する 42
・棚卸資産の分類を悪用すると… 42
《ひとこと》ルールの明文化 44
2 トレーディング目的で保有する棚卸資産とは? 45
1 トレーディング目的で保有する、の意味 45
2 市場(マーケット)の存在が前提になる 45
《ひとこと》トレーディングとは 46
3 「売ったり」「買ったり」できる市場でなければならない 46
4 自由な売買を妨げるそのほかの要因もチェックする 47
5 再度会社の意思を確認しましょう 48
3 通常の販売目的で保有する棚卸資産とは~棚卸資産全体の理解を前提に 49
1 新基準ではどのように定義しているのか 49
2 棚卸資産の範囲は半世紀近く前の意見書が定めている 50
・「財貨」「用役」の意味をしっかり押さえておこう 51
・連続意見書で定める棚卸資産の4つの定義 52
3 商品、製品、半製品などの意味を再確認しておこう 53
・商品とは 53
・製品とは 54
《ひとこと》商品と製品の違い 54
・半製品とは 54
・原材料とは 55
・仕掛品とは 55
《豆知識》半製品と材料の違い 56
4 製造目的なのに通常の販売目的で保有する棚卸資産とは? 57
5 工事や作業も通常の販売目的で保有される 57
《豆知識》建設関係の勘定科目 58
6 国際的な会計基準と日本基準の違い 58
《ひとこと》Pass as minor 59
4 棚卸資産と混同しやすい資産、わかりにくい棚卸資産 60
1 棚卸資産と混同しやすいその他の資産 60
・使用開始前の有形固定資産 60
・1年以内に償却が終了する減価償却資産 61
・売却目的で保有する使用中止資産 61
2 その他の資産と混同しやすい棚卸資産 62
・一部分の目的が異なる資産 62
・固定資産の廃材を使用する場合 63
・包装用品や荷造用品 64
・土地、建物などの不動産 64
・その他 65
5 棚卸資産の保有目的を変更するには? 66
1 保有目的の変更にはよほどの事情が必要とされる 66
2 トレーディング目的で保有する棚卸資産への変更は慎重に 66
3 保有目的の変更を考えたときに登場する別の会計基準 68
4 保有目的の変更が認められる正当な理由とは? 69
・トレーディング目的で保有する棚卸資産から通常の販売目的で保有する棚卸資産への変更 69
・通常の販売目的で保有する棚卸資産からトレーディング目的で保有する棚卸資産への変更 70
5 合併などの企業結合が行われた場合の分類 71
・棚卸資産を入手する可能性のある企業結合 71
・企業結合は「取得」「持分の結合」「共同支配企業の形成」「共通支配下の取引」のどれに該当する
のか? 72
・企業結合の類型によって決まる棚卸資産の分類 74
3章 通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価に関する会計
1 棚卸資産の評価基準 78
1 棚卸資産の評価基準が低価法に統一された 78
2 具体的な3つの評価基準 79
・評価基準とは 79
・取得原価基準とは 79
・外部から取得した棚卸資産の取得原価 80
(1)購入した棚卸資産の取得原価 80
(2)交換によって取得した棚卸資産 84
(3)特別な価額で取得した棚卸資産 84
《豆知識》現金払いとカード払い 85
・自社で製造した棚卸資産の取得原価 86
・低価基準 88
・低価法は原価法の例外から一部へ 88
《豆知識》低価法? 低価基準? 93
・時価基準 93
3 評価基準の変更とその背景 94
・原則が低価基準に変更 94
・今後、決算書の注記は必要? 94
・評価基準を一本化~背景にあった国際的な批判 95
・従来の会計処理の背景にあった考え方 96
・取得原価に対する見方の転換~回収可能性という考え方 96
《豆知識》固定資産の減損会計 98
・収益性の下がった原因を分析することは重要か? 98
《豆知識》会計基準の設定のための会議 98
《豆知識》収益性とは販売価格? 99
2 評価替えが必要なのはどんなとき? 101
1 「時価<帳簿価額」の関係が成立したとき 101
2 時価の定義 101
・「公正な」とは? 102
・「価格」と「価額」の違いは? 102
《豆知識》価格と価額の発音は? 103
・「合理的に算定された」とは 103
・以上を踏まえて定義を解釈すると… 104
3 時価は将来を想定したもの 104
4 事務用消耗品などの棚卸資産も評価替えをするか? 106
5 「時価の下落」=「収益性の低下」とはならない場合 107
・時価は下落しているけれど、収益性は低下していないケース 108
・時価は下落していないけれど、収益性が低下しているケース 108
《豆知識》資産の会計処理を決めるのは投資の性質 109
3 評価額を計算しよう 110
1 低価法を実践するポイント 110
2 簡単な例で低価法を再確認しよう 111
《豆知識》実地棚卸とは? 112
3 棚卸資産の評価に使用される時価とは 112
4 正味売却価額の計算 113
・原則として正味売却価額を使用する 113
・売価とは~会計上の市場、売却市場の市場価格 113
・見積追加製造原価と見積販売直接経費 114
・いつの正味売却価額を計算する? 116
5 売却市場の市場価格がない場合はどうするのか 117
《豆知識》投資の失敗が判明するとき 118
《豆知識》正味実現可能価額→正味売却価額 118
・合理的に算定された価額とは? 118
・算定が合理的であれば「合理的に算定された価額」 119
・市場がとても閉鎖的な場合、市場がまだ想定できない場合~販売見込の活用 119
6 正味売却価額に代えて再調達原価を使用する場合 122
・再調達原価とは 122
・なぜ付随費用を取得原価と合わせるのか 123
・正味売却価額に代えて再調達原価を使用するための条件 124
・継続適用が条件になる 125
・再調達原価のほうが把握しやすい場合とは? 125
《豆知識》「継続性の原則」とは 125
・再調達原価には最終仕入原価も含む 126
・どんな資産でも条件さえ満たせば再調達原価を使用できる 127
・再調達原価を使用する場合も文書化が必要 128
(1)過去のトレンドを利用する方法 128
(2)会社の方針を利用する方法 129
(3)市場の状況を利用する方法 130
・付随費用と重要性 130
7 複数の市場が存在する棚卸資産の扱いは? 131
・その他の具体例 131
・複数の売却市場がある棚卸資産を評価する場合の留意点 132
8 売価還元法を使用している場合 133
・売価還元低価法の特例 134
《豆知識》売価還元法と売価還元低価法の違いとは 134
・売価還元低価法だと正味売却価額の計算が不要なのはなぜ? 135
・売価還元法を採用する場合の正味売却価額の計算 135
9 期末の正味売却価額が異常値だった場合 136
10 正常な状態にない棚卸資産の評価 137
・正常な状態でないとは 137
・営業循環過程から外れた資産の評価 137
・帳簿価額を処分見込価額(ゼロまたは備忘価額も含む)まで切り下げる方法 138
・棚卸資産が一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法 138
《豆知識》回転期間を計算してみよう 139
11 合理的に算定された価額も計算できなかった場合の対応は? 140
《ひとこと》滞留資産の評価と内部統制 140
12 計算された正味売却価額がマイナスだった場合の対応 141
・正味売却価額がマイナスとなるケース 141
・引当金を計上するための4要件 142
・正味売却価額がマイナスの場合の引当金と4要件 142
13 保有している棚卸資産はひとつ残らず評価するのか? 143
14 最も大切なのはデータの整備 144
4 評価の単位を決めよう~個別かグルーピングか 146
1 原則は「すべての棚卸資産を個別に評価」する 146
2 グループで判断する場合もある 147
(1)補完的な関係にある複数の棚卸資産の売買を行う場合(グルーピングその1) 147
(2)同じ製品に使われる材料、仕掛品及び製品をまとめる場合(グルーピングその2) 150
3 グルーピングは継続的に 151
5 評価損を計上した翌期の会計処理~洗替え法と切放し法 153
1 「洗替え法」と「切放し法」 153
・洗替え法とは 153
・切放し法とは 154
2 洗替え法と切放し法の選択 154
3 洗替え法と切放し法のどちらを選べばよい? 155
(1)棚卸資産の簿価切下額をシステムに反映することができない場合 155
(2)棚卸資産の簿価切下額をシステムに反映できる場合 156
4 収益性低下の要因と会計処理方法 157
5 どちらを選択したかで結果が変わる場合もある 158
6 固定資産の減損会計と棚卸資産の簿価切下げの違い 160
7 洗替え法の適用には批判的な見方もある 161
4章 トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価に関する会計
1 トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準 164
1 会計処理は「売買目的有価証券」に準じる 164
2 参照する会計基準の一覧 165
3 売買目的有価証券の定義を確認しておこう 165
4 具体的な会計処理について知っておこう 166
・使用される時価はいつのもの? 167
5 翌期の会計処理について知っておこう 168
・同一の棚卸資産を異なる区分で保有する場合 168
《豆知識》会計処理の背景~企業にとっての成果という考え方 169
6 金融商品実務指針の設例の応用と保有目的の変更処理 170
2 トレーディング目的で保有するためにはさまざまな条件がある 174
1 ここでも「金融商品に係る会計基準」が参照される 174
2 活発な市場の存在と経営者の意思 174
3 さらに望ましいのは客観的な要件も満たすこと 176
(1)棚卸資産のトレーディングを業としていることが定款の上から明らか 177
(2)トレーディング業務を日常的に遂行できる人材から構成された独立の専門部署(関係会社や
信託を含む。)によって棚卸資産が保管・運用されていること 177
・上記の2要件を満たさない場合は? 177
《ひとこと》次善の策のご提案 178
4 トレーディング目的で保有する棚卸資産に関する開示事例 178
・基準を早期適用した会社の事例 178
5章 決算書ではどのように開示されるか
1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の開示 182
1 開示とは、会計処理結果の表現 182
2 簿価切下額の損益区分~通常の場合 183
・販売費で処理してはいけないの? 184
3 簿価切下額の損益区分~特別の場合 184
《参考》サンプル品として使用する棚卸資産の評価 186
・従来の強制評価減との関係 186
・特別な簿価切下額は切放し法で処理する 187
4 洗替え法における戻入額の計上区分 188
5 従来の計算区分との対比 190
6 簿価切下額の表示方法 191
・区分掲記する方法 192
・注記をする方法 192
《ひとこと》開示のルールは基準公表前後で変化なし 194
2 トレーディング目的で保有する棚卸資産の開示 195
1 「棚卸資産の評価に関する会計基準」から 195
2 トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益とは? 196
3 「原則として」売上高に計上とされているが、例外はあるのか? 197
・棚卸資産のトレーディングを主たる事業としている場合 197
・棚卸資産のトレーディングを主たる事業とはしていない場合 197
4 表示と日常的な管理は区別して考える 198
3 早期適用会社の事例を見てみよう 200
6章 適用初年度に注意しなければならないこと
1 基準の適用時期について確認しておこう 202
1 平成20年4月1日以降開始事業年度からスタート 202
《豆知識》公開草案とは 203
2 早期適用する際の注意点 203
(1)一部適用は認められないこと 204
(2)連結財務諸表における連結子会社にも適用すること 204
(3)期首に限らず受入準備が整った段階から早期適用ができること 205
《ひとこと》四半期報告制度の適用開始はいつ? 206
《豆知識》中間・年度の首尾一貫性 207
3 適用が強制される会社と望まれる会社 208
2 適用初年度だけ認められる例外処理に注意しよう 210
1 適用初年度のみ特別損失処理が認められる 210
2 特別損失計上額の計算方法 211
(1)期首の在庫の評価から適用したとみなす方法 211
(2)期末の在庫の評価から適用する方法 211
3 例外処理の簿価切下額は切放し法で 215
《豆知識》特別利益や特別損失の性格 216
《豆知識》従来も評価方法の変更時に例外処理はあったの? 216
4 例外処理を採用するため早急に準備しなければならないこと 216
5 トレーディング目的で保有する棚卸資産に例外処理はある? 218
3 基準の適用は正当な理由による会計方針の変更に当たる 219
1 会計方針の変更とは 219
2 会計方針の変更には正当な理由が必要 220
3 会計方針を変更したら明らかにしなければならない 220
・金融商品取引法適用会社の場合 220
《参考》適用される規則の一覧 221
・会社法適用会社の場合 222
《ひとこと》棚卸資産を持っていない会社は? 222
4 監査報告書における追記情報 223
《ひとこと》監査報告書の構成 224
4 四半期報告制度に対応するには 225
1 四半期報告制度とは? 225
2 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用は第1四半期から 225
3 四半期決算における簡便な棚卸資産の評価とは 226
・収益性の低下が明らかな棚卸資産の検討 226
・処分見込価額まで切下げ済みの棚卸資産 227
4 四半期決算における洗替え法と切放し法 227
5 四半期決算における会計方針の変更 228
《ひとこと》年度と四半期の貸借対照表の表示 230
7章 棚卸資産会計に関連するその他の留意事項
1 会計基準が適用されるか判断が微妙な資産 232
1 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の範囲から除外されたもの 232
2 排出クレジットの会計処理 234
3 販売用ソフトウェアの会計処理 236
4 売買目的有価証券の会計処理 237
5 未成工事支出金の会計処理 238
2 実地棚卸の方法とポイントを改めて確認しよう 240
1 実地棚卸の意義と目的を知っておこう 240
(1)残高と売上原価(または製造原価)を確定する 240
(2)棚卸資産の状態を確認する 242
・基準日を明確にする 243
2 実地棚卸の方法 244
・タグ方式 244
・リスト方式 246
・バーコード方式 246
3 実地棚卸にあたっての留意点 247
・計画が成否を大きく左右する 247
・現場や関係する帳簿類の整備 248
・実地棚卸中の荷動き 249
・ダブルチェック 250
・品質状態のチェック 250
・網羅的な棚卸の確認作業~タグ・コントロールの重要性 250
4 実地棚卸のフォローもおろそかにできない 251
5 棚卸立会を行う監査人の立場から 253
・重要な内部統制 253
・特殊な棚卸資産または棚卸対象外資産 254
(1)売上済未出荷品 254
(2)未検収品 255
(3)預け品 256
(4)預かり品 258
8章 中小企業のための棚卸資産会計
1 中小企業の会計に関する指針~その背景と基本方針 260
1 日本の中小企業の現状 260
2 特別な会計基準の必要性 261
3 指針以外の法律等にある中小企業への配慮 262
《豆知識》連結計算書類とは? 263
《参考》注記表に記載される項目(会社計算規則129条1項より) 264
4 指針ができるまで 264
5 中小企業の会計に関する指針の公表 266
6 「中小企業の会計に関する指針」の対象会社 267
《豆知識》監査報告書の意見の種類 268
7 法人税法で定める処理ではだめなのか? 268
8 理論と実務のはざまで、指針が目指したもの 269
9 指針を利用する場合の注意点 269
《ひとこと》指針のエッセンス 270
2 「中小企業の会計に関する指針」の各論~棚卸資産の会計処理 271
1 中小企業特有の会計処理 271
(1)簿価切下げを実施する要件 272
(2)棚卸資産の評価方法 274
《参考》最終仕入原価法に問題のあるケース 275
(3)簿価切下額の表示 276
2 指針におけるその他の規定 276
3 個別注記表の記載例 277
9章 法人税法における棚卸資産の会計処理
1 法人税法上の規定の特徴を知っておこう 280
1 目的が異なるふたつの会計がある 280
2 財務会計と税務会計の違い 281
《ひとこと》税務は適用漏れには太っ腹? 283
2 税務会計特有の処理 284
1 評価基準は企業の選択にゆだねられる 284
・原則として評価方法の届出が必要 284
《豆知識》会社計算規則は微妙な立場 285
・特別な評価方法の届出 286
・税務会計だけが認める棚卸資産の評価方法 286
《豆知識》財務会計と税務会計 287
2 低価法のグルーピングに関する相違点 288
《ひとこと》後入先出法の切放し法 289
3 簿価切下額の計上区分 290
4 売価還元法に関する相違点 290
・税務会計も売価還元低価法で低価法の判定を省略できる? 291
5 税務会計の調整勘定 292
6 トレーディング目的で保有する棚卸資産は範囲外 292
3 より具体的な規定、詳細に明文化した規定 293
1 数値基準の具体的な設定 293
・購入した棚卸資産の付随費用 294
・製造した棚卸資産の付随費用 295
・原価差額の調整計算 296
2 「暗黙の了解」を明文化する 296
・付随費用の明確化、非製造原価の明確化 297
・棚卸資産の受払帳簿の作成義務 297
・購入代価が決まらない棚卸資産 298
・個別法の採用 298
10章 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正案について
1 改正の概要を知っておこう 302
1 改正案が公表された 302
2 改正が必要な背景にはどんなことがある? 303
2 棚卸資産の評価方法 304
1 評価方法が決まらないと決算書は作れない 304
2 認められた4つの評価方法 305
(1)個別法 306
(2)先入先出法 307
(3)平均原価法 308
(4)売価還元法 310
3 評価方法の採用単位 312
《豆知識》最終仕入原価法の取扱い 314
3 後入先出法の廃止とそれに伴う影響 315
1 後入先出法の廃止と特徴 315
・後入先出法の長所 315
・後入先出法の短所 316
・後入先出法の採用企業数と廃止の決定 317
2 後入先出法を採用している企業の対応 318
・初年度の特例処理 318
・変更による影響額の簡便的な計算方法 319
巻末資料
1 棚卸資産の評価に関する会計基準 326
2 早期適用会社の事例を見てみよう 341
さくいん 353
著者プロフィール
松尾絹代
公認会計士。1970年東京都世田谷区生まれ。90年東京大学理科I類入学、工学部船舶海洋工学科進学。92年度ミス日本。NHKハイビジョンニュース等でキャスターをつとめるほか、バラエティ番組にも出演。95年ブルガリ・ジャパン(株)入社、数字を通して会社全体を見通せる面白さに気付き、公認会計士受験を決意。99年公認会計士2次試験に合格、太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)に入所。8年間企業監査に従事後、情報発信業務担当。2008年7月より金融庁総務企画局企業開示課に、企業会計専門官として出向。コンバージェンスに揺れる会計に新たな立場で関与する。