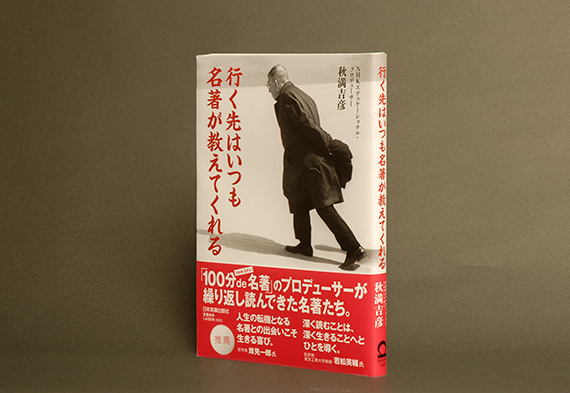去る3月6日、東京は池袋のジュンク堂書店で、NHK Eテレの人気番組「100分de名著」のプロデューサーである秋満吉彦さんと、能楽師の安田登さんの対談が行われました。話題は秋満さんの近著『行く先はいつも名著が教えてくれる』で取り上げられた『夜と霧』(フランクル)や『モモ』(エンデ)といった名著の読み解きから、名著によって得られた仕事観や人生観、さらには日本人の働き方、文化論にまでおよびました。この対談のダイジェストを、前・後編に分けて掲載します。
『行く先はいつも名著が教えてくれる』刊行記念スペシャル対談 秋満吉彦(NHK Eテレ「100分de名著」プロデューサー)×安田登(能楽師) 【前編】
フランクル『夜と霧』との出会いが人生を変えた
秋満吉彦氏(以下、秋満):高校生のとき、サルトルがアイドルでした。研究者になりたくて、大学の哲学科に進みましたが、出来が悪かったんですね。自分の実力では研究者になるのは無理だなと感じてはいましたが、普通の就職はしたくなかった。だから研究者志望を言いわけにして「就職活動になんか興味はない」とグレていて、周囲にもそれを吹聴していました。
そんなとき、なぜか僕が悩んでいることに気がついていた女性の後輩がいて、彼女が教えてくれたのが『夜と霧』でした。図書館で借りて読んだのですが、この本が僕の人生を大きく変えました。
これはナチスによる強制収容所での出来事を描いた本ですから、とてもつらい本です。でも読み進めるうちに、だんだんと「これほどの極限状態でも、こんな生き方ができるすばらしい人たちがいるんだ」というポジティブな気持ちになってくる。
せっかく安田さんがいらっしゃるので、拙著にも引用した部分を朗読していただきましょう。
安田登氏(以下、安田):わかりました。読んでみましょう。
「人生から何をわれわれはまだ期待できるかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれに期待しているかが問題なのである。すなわちわれわれが人生の意味を問うのではなくて、われわれ自身が問われた者として体験されるのである。人生はわれわれに毎日毎時問いを提出し、われわれはその問いに、詮索や口先ではなくて、正しい行為によって応答しなければならないのである。人生というのは結局、人生の意味の問題に正しく答えること、人生が各人に課する使命を果たすこと、日々の務めを行うことに対する責任を担うことに他ならないのである」(フランクル『夜と霧』(霜山徳爾 訳) みすず書房から)
秋満:格調高い朗読をありがとうございました。みなさん拍手を。
この一節にぶつかったときに、僕は頭を殴られた感じがしました。人生の見方が180度変わった。普通人間は、困難なことが起きると「なぜ私がこんな目に遭わなければいけないのか」と人生の意味を問うてしまう。でもフランクルは、「あなたは人生を問うてはいけない。人生から問われているんだ」と言う。常識が完全に逆転させられて、「なんだこれは!」と背筋がぞくぞくする感じを味わいました。
つまり、僕はそれまで、自分のやりたいことだけをやりたいとしか考えてこなかった。しかしこの本に出会って、もし自分が人生から何かを問われているのだとしたら、何を問われているんだろう、と考えるようになりました。
それにはまず、周りの人たちが自分に何を求めているかを知ろうと、信頼できる教授や先輩、同級生に「俺は何に向いている?」と聞いて回りました。僕があまりに熱心に聞いて回るので「お前どうかしたのか?」と言われましたが(笑)。
その結果、どうやら自分は聞き上手で、人の話をまとめたりわかりやすく伝えたりすることに向いているらしい、ということがわかった。そうして就職先に選んだのがマスコミ業界でした。『夜と霧』に出会わなかったら、マスコミ業界にいなかったでしょう。
促成か、ゆっくり育てるか
秋満:そのときに実感したことがあります。それは「こうなりたい」とか、「こうなったら楽しいだろうな」と、自分の願望だけで取り組むことにはそれほど力が出ない、ということです。一方で、「世の中から求められている」と思えた事柄に対しては、ある種の確信をもってがんばることができる。
それまではマスコミなんて考えたこともなかったので、時事問題などにはあまり関心がなく、新聞もほとんど読まなかったのですが、就職試験の前は、付け焼刃とはいえものすごく勉強しました。いま思うとよくNHKに通ったなと思います。
このことを境に僕の本を読む態度、姿勢が決定づけられたと言っていいと思います。つまり、本を情報として読むのではなくて、自分に問いかけてくるものとして読むようになりました。もちろん、単純に楽しみのために読む本もありますが、古典を読むときには、「これは自分のことを書いているのに違いない」と思って読むと本当にビンビン伝わってきます。人類の知恵というか、生きていくためのヒントが詰まっているんですね。
「本は高い」と言う人もいますが、ランチ1回分か2回分の出費ですよね。それで人生が変わるかもしれないのですから、ぜひ皆さんも古典に触れてほしいです。
安田:おっしゃる通り、自分が何に向いているかというのは、自分で無理矢理に探すものではありませんね。いつの間にか、内発的に現れてくるものです。孔子ですら「五十にして天命を知る」と言っているくらいなんですから。
そういう意味では、子どもに「大きくなったら何になりたい」なんて聞かないほうがいい。あれはひどい質問ですね、子どもに選択肢なんてほとんどないのに。あんまり聞かれると、かえって自分のことがわからなくなってしまう。私が育った地域では、子どもは大人になったらほとんどが漁師になるので、何になりたいかなんてまったく聞かれませんでした。これは本当に幸運でした(笑)。
能には子方(こかた)という子どもがやる役があるんですが、いわゆる「上手く」演じることはさせないんです。一所懸命にやることだけを求めます。彼らが60、70、80歳まで舞台に立ち続けて、そして死ぬまで成長するようにするためには、子どものころは上手くさせないほうがいい。テレビなどでも上手い子役は消費されてしまうでしょう。能は消費されることを嫌います。急かさないで、ゆっくり育てる。
これは人だけでなく「お道具」と呼ばれる能の楽器でもそうです。35歳のときに鼓の革を買ったのですが、最初に「いまこの鼓の革はまったく鳴りません。50年間、毎日打つと鼓は鳴るようになります。1回鳴ると600年はもちます」と言われました。ただし早く鳴らす方法もあって、張扇(はりおうぎ)でタンタンとたくさん叩く。すると数か月で音が出るようになる。ところがこの方法では、10年ぐらいしか鼓がもたないそうなのです。ゆっくりじっくり育てて長い間使うか、促成して消費されてしまうかです。

『モモ』と能と「耳なし芳一」
秋満:今日は安田さんとのトークですからぜひ能に関わるお話をしたいと思います。
拙著でも取り上げたミヒャエル・エンデの『モモ』は、非常に能的な物語だと思います。そして『モモ』と似た構造を持つ物語が日本にもあって、意外に思われるでしょうが、皆さんご存知、小泉八雲の怪談「耳なし芳一」です。これもまさしく能的な世界と言えるでしょう。
『モモ』と「耳なし芳一」、それに能も、主人公が「死者と出会う物語」です。能の主役であるシテは死者、亡霊です。その亡霊の声を聞くのがワキです。
安田:能のワキは脇役という意味ではなくて、「分ける」というところからきています。能では、幽霊が住む世界と人間が住む世界は分かれていて、本来、出会うことはない。しかしワキは、その境界にいるから出会うことができる。あの世とこの世のはざま、境界線にいる存在がワキ。芳一はまさにそんな存在ですね。
秋満:『モモ』と「芳一」は「耳」が大事なテーマになっている点でも共通しています。『モモ』の主人公の小さな女の子、モモは、いろんな人の話を聞いてあげる「理想的なカウンセラー」「究極の聞き上手」として登場します。また、モモが住みついた街の円形劇場のいちばん底で、宇宙の星々から聞こえてくる音楽を聞くというとても美しいシーンがありますが、円形劇場は「宇宙の声を聞く大きな耳」のメタファーでしょう。そのほかの要素からも『モモ』は、全体を通して「全身で耳をかたむける」という話なのです。
モモは時間の国で死者に出会って、その言葉を聞きます。盲目の芳一も亡霊の言葉を聞き、琵琶を奏でる。最後には耳を取られてしまいますが。
つまり現実のこの世と、人智のおよばない異界をつなぐものとしての「耳」、そして「聞く」ということが重要なテーマになっているんです。
「耳で聞く」ということ
秋満:近代哲学というのはすごく視覚的なものです。目で見て分析して、差異を言語化して、コントロールできるように並び変えます。ところが音は時間の経過として連続し、流れているから分節できない。だから音というのは、現実世界では分析できない、異界とつながりうるものとしてあるのではないか。
「100分de名著」では5月に安田さんを指南役として『平家物語』を取り上げます。『平家物語』もまさに音であり、語りです。劇的に物語が動く場面では、闇や音が鍵を握っている。
現代社会に生きる人間は視覚中心に動いています。人の話やいろいろな音をじっくりと耳で聞いて、それらをいったん受けとめるということをしなくなっている。私たちは、音や語りというものを、もっと取り戻すべきなんじゃないかと思います。
安田:月食とか日食、私たちはあれを一所懸命見ようとしますね。でも、殷の時代の甲骨文などを読むと、月食は見るものではなく、聞くものでした。実は私は日食を「聞いた」ことがあります。1991年に、ハワイ島でのことです。
日食が始まる直前、鳥がすごい勢いで鳴きだしたんです。ところが日食が始まるとそれがピタッと止む。それはキラウエア火山が噴火したばかりだったので、遠くの稜線が真っ赤な龍のように見えた。そして日食が終わると、またワアーっと鳴きだすんです。非常に劇的な変化でした。
日食を見るためのすりガラスなどもない昔の人にとっては、日食は目で見るのではなくて、耳で聞くことによって変化を感じるものだったのです。
秋満:哲学者のハイデガーは、近代哲学を批判するなかで、聞くということについて「近代は世界のすべてが像化している世界像の時代だが、それを見るのを止めにして、存在の声に耳を澄ませ」ということを述べています。もっとも奥深いことは、見えるものではなく聞こえてくるものだ、ということなんですね。
(後編に続く)