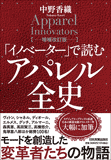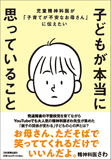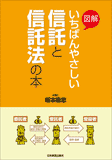
図解 いちばんやさしい信託と信託法の本
| 発売日 | 2008.12.24 |
|---|---|
| 著者 | 坂本隆志 |
| 判型 | A5判/並製 |
| ページ数 | 248 |
| ISBN | 978-4-534-04475-4 |
| 価格 | ¥1,760(税込) |
まったく知識のない方でも、信託の仕組みと新信託法の基本がビジュアルにやさしくわかる本。80年ぶりに大改正された信託法の影響、自己信託など新たに可能になった信託のスキームもコンパクトにまとめました。金融・不動産業等の実務家必読の1冊です。
≪章立て≫
第1章 信託の仕組みと信託法の基本
第2章 信託の設定方法と信託財産
第3章 受託者の権利・義務と責任
第4章 受益者の権利行使と委託者の権限
第5章 信託の変更および終了
第6章 新信託法で可能になった信託
第7章 信託に関する業法上の規制
第8章 信託ビジネスの新たな展開
オンラインストアで購入する
テキスト採用など、大量・一括購入に関するご質問・ご注文は、弊社営業部(TEL:03-3268-5161)までお問い合わせください。
詳細
第1章 信託の仕組みと信託法の基本
1 そもそも「信託」とは何ですか
2 信託はどのように生まれたのか
3 なぜ信託法は全面改正されたのか
4 信託には商事信託と民事信託がある
5 自益信託と他益信託のちがいは
6 なぜ日本では民事信託が普及しなかったのか
7 預金型商事信託とはどんなものか
8 運用型商事信託とはどんなものか
9 転換型商事信託とはどんなものか
10 転換型商事信託のメリットはなにか
11 事業型商事信託とはどんなものか
第2章 信託の設定方法と信託財産
12 契約による信託の設定方法
13 「信託」と認定される取引とは
14 遺言による信託もできる
15 自己信託とはどのようなものか
16 受動信託とはどのようなものか
17 脱法信託・訴訟信託は禁止される
18 詐害信託は取り消される
19 信託財産は誰のものか
20 信託財産の独立性も受託者次第
21 信託財産の範囲の決め方と公示の仕方
22 信託財産も破産することがある
第3章 受託者の権利・義務と責任
23 受託者にはどのような権限と義務があるか
24 受託者の善管注意義務とはどのようなものか
25 受託者の忠実義務とはどのようなものか
26 利益相反行為とはどのような行為か
27 禁止される競合行為とはどのようなことか
28 受託者の公平義務とはどのようなものか
29 受託者の分別管理義務とはどんな義務か
30 信託事務の処理は第三者に任せてよいか
31 帳簿等の作成・保存義務と報告義務
32 受託者が負う損失てん補責任と原状回復責任
33 受託者の任務終了と受託者の変更
34 受託者が破産したときはどうなるか
35 受託者が2人以上いるときはこうする
第4章 受益者の権利行使と委託者の権限
36 受益者にはどのような権利があるか
37 報告請求権と帳簿等の閲覧請求権とは
38 受益権は時効によりなくなってしまうのか
39 受益権は原則として自由に譲渡できる
40 受益者が2人以上いるときの意思決定の方法
41 信託管理人とはどんな人か
42 新法における委託者の権利は縮小された
43 委託者の相続人の地位はどうなったか
第5章 信託の変更および終了
44 信託の変更はどんなときに行えるか
45 信託の併合とはどういうことか
46 信託の分割とはどういうことか
47 受益権取得請求権とはなにか
48 どのような場合に信託は終了するか
49 信託の清算手続きはどのように行われるか
第6章 新信託法で可能になった信託
50 限定責任信託とは何か
51 限定責任信託に関する法規制
52 限定責任信託等の会計
53 受益証券発行信託とは何か
54 特定受益証券発行信託とは
55 受益証券発行限定責任信託と会計監査人
56 目的信託とは何か
57 遺言代用の信託とは何か
58 後継ぎ遺贈型信託とは何か
59 後継ぎ遺贈型信託と税制
60 セキュリティ・トラストとは何か
61 信託社債とは何か
第7章 信託に関する業法上の規制
62 なぜ信託業法は全面改正されたのか
63 運用型信託会社とはどんな会社か
64 管理型信託会社とはどんな会社か
65 信託契約代理店に関する規制
66 自己信託を登録しなければならない場合
67 信託銀行とはどんな銀行か
68 投資信託とは何か
69 信託に関する金融商品取引法の規制
70 福祉型信託に関する業法規制はどうなるのか
第8章 信託ビジネスの新たな展開
71 知的財産権信託の活用法
72 リバース・モーゲージと信託の利用
73 排出権の信託とは何か
74 エスクロー信託とは何か
著者プロフィール
坂本隆志
1975年生まれ。1999年司法試験合格。2000年東京大学法学部(第2類)を卒業し、司法研修所に入所、2002年弁護士登録。2006年東京弁護士会法制委員会副委員長に就任(現任)。個人再生事件等の処理に長らく従事し、最近は企業の粉飾決算事件の処理にも関与している。取得資格は、弁護士のほか、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナー、マンション管理士など多数。信託法の制定家庭では、東京弁護士会法制委員会委員(当時)として、委員会としての意見形成に深く関与した。主な著作に、『図解個人再生徹底活用マニュアル』(大和出版、共著)がある。