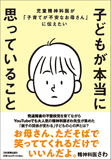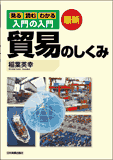
入門の入門 最新 貿易のしくみ
| 発売日 | 2008.03.19 |
|---|---|
| 著者 | 稲葉英幸 |
| 判型 | A5判/並製 |
| ページ数 | 176 |
| ISBN | 978-4-534-04368-9 |
| 価格 | ¥1,650(税込) |
92年発売の同タイトルの最新版。取引全体の流れから、契約、貿易条件、船積み、決済、保険、外国為替…まで、貿易のしごとをする人なら知っておきたい事項を図解をもとにコンパクトに解説。これ1冊で、しごとの内容や最新トピックが丸ごと理解できます。
≪章立て≫
第1章 モノ、カネ、カミで「貿易取引の流れ」をつかむ
第2章 「輸出入契約」と「許認可」のしくみ
第3章 「貿易条件」の基本を知っておく
第4章 モノを運ぶ「通関・船積・荷卸し」のしくみ
第5章 「代金決済」と「船積書類」のしくみ
第6章 「貿易保険」「海上保険」とはどういうものか
第7章 「外国為替」と「貿易金融」の基本
第8章 「貿易クレーム処理」と「特殊な貿易取引」
オンラインストアで購入する
テキスト採用など、大量・一括購入に関するご質問・ご注文は、弊社営業部(TEL:03-3268-5161)までお問い合わせください。
詳細
第1章 モノ、カネ、カミで「貿易取引の流れ」をつかむ
1 貨物(モノ)の流れと代金(カネ)の流れ 16
貿易取引の2つの基本的な流れをつかむ
2 書類(カミ)の流れ 17
モノ・カネの流れは書類(カミ)が誘導する
3 信用状という重要な書類(カミ)の役割 18
信用状(L/C)は貿易のリスク管理の有力手段
4 送金決済における書類の流れ 19
送金決済では信用状決済と書類(カミ)の流れが異なる
5 後払い送金と銀行保証状(カミ)の役割 20
後払い送金ではL/Gを利用する
6 貿易関係機関(ヒト)の役割 21
モノ・カネの流れを支える貿易関係機関
7 国際ルールの活用 22
貿易のしくみを支える、いろいろなルールと役割
8 貿易取引とリスク管理 23
リスク管理の目で貿易のしくみをつかむ
9 取引先の開拓方法 24
世界各国の見本市やジェトロ等の機関を利用して情報を集める
10 相手先の信用調査のやり方 25
調査機関や銀行を利用するほか、自分で確かめることも必要
11 海外市場調査のやり方 26
資料や情報の分析、実地見聞のほか、商社の利用も検討する
12 輸出マーケティングと販売政策 27
代理店の利用を考える場合は、選定に慎重な調査を要する
13 銀行取引を始めるには 28
輸出・輸入いずれの場合にも、いくつかの約定書の差入れが求められる
14 日本の代表的貿易振興機関 29
中心的役割を果たすジェトロと、輸入促進のためのミプロが代表的存在
COLUMN 二重ガラス窓の空輸トラブル 30
第2章 「輸出入契約」と「許認可」のしくみ
1 成約までのステップとは 34
通常は、売込みから引合い、オファーを通じて契約に至る
2 契約までの予備的交渉とポイント 35
交渉の過程では、後のトラブルを避けるために書面でのやりとりが大切
3 ファーム・オファーとカウンター・オファー 36
回答期限を明示するファーム・オファーでは、期限内の取消し等はできない
4 確認条件付きオファーとは 37
相手から承諾があっても、こちらの確認がなければ契約は不成立に
5 交渉から契約時に交わす書類とは 38
引合い、見積り、申込み(オファー)等のやりとりを経て契約書作成に
6 契約書の作成と留意点 39
通常は2通作成。双方のチェック、サインの後、各々が1通ずつ保管
7 一般取引条件とは何か 40
契約を交わすときは、企業独自の権利・義務を記した裏面にも要注意
8 納期の管理に注意する 41
トラブルのもととなりがちな重要要件だけに、遅延防止に留意する
9 品質保証とはどういうものか 42
貿易クレームの大半は品質に関するもの。売買の仕方で保証方法は異なる
10 日本の為替・貿易管理とその体系 43
「外国為替及び外国貿易法」に基づき、原則自由が基本になっている
11 輸出管理とその狙い 44
特定の取引では、事前の許可や承認が求められることも
12 ワッセナー協約とは 45
国際的に武器の輸出を管理するための協約
13 輸出に関するキャッチオール規制 46
大量破壊兵器不拡散のための輸出規制
14 輸入管理とその狙い 47
輸入禁制品のほか、輸入割当や承認、通関時の確認等で運用される
15 国内関係法による輸入規制とは 48
関税定率法をはじめ、各省庁が担当する法令がある
16 輸入割当品目と輸入承認手続き 49
割当品目の輸入では、割当の許可に続いて輸入承認が必要になる
17 輸出入許可・承認手続きの電子化 50
輸出入者は電子端末から許認可申請ができる
第3章 「貿易条件」の基本を知っておく
1 インコタームズとは何か 54
国際商業会議所によって定められ、取引条件の統一的な解釈を図る
2 FOB条件とは 55
貨物が本船の手すりを通過すれば、輸出者の引渡し義務は完了する
3 FCA条件とは 56
輸出者が指定した場所・地点で輸入者指定の運送人に貨物を引き渡す
4 CFR条件、CIF条件とは 57
運賃を輸出者が支払うのがCFR。CIFでは保険料までを負担する
5 CPT条件、CIP条件とは 58
FCAに加えて、輸出者が運賃や保険料を支払うのがCPTとCIP
6 EXW条件、FAS条件とは 59
EXW条件では、輸入者が輸出通関や輸出承認等の手続きを行なう
7 DAF条件とは 60
陸続きの国との取引で、鉄道やトラック輸送をする場合に利用される
8 DES条件、DEQ条件とは 61
CFR、CIFに似ているが、輸出者の危険負担の限界が異なる
9 DDU条件、DDP条件とは 62
最大の義務を負担するため、輸出者は検討を要する条件
10 コンテナ貨物の貿易条件 63
コンテナ積みでは、FCAやCPT、CIPを使う
11 航空貨物の貿易条件 64
航空貨物の場合は、FCAやCPT、CIP条件を使う
12 改正アメリカ貿易定義とは 65
インコタームズとはFOBが異なるので、米国向け取引では注意が必要
13 所有権と危険の移転とは 66
双方の間で、予め商品の所有権とリスクの移転を取り決めておく
14 定期船、不定期船とは 67
鉄鉱石や石炭など、大量のバラ積み貨物では不定期船が利用される
15 海上運賃のしくみ① 68
定期船には同盟船と盟外船があり、いずれもバース・タームが基本となる
16 海上運賃のしくみ② 69
運賃の建値は、重量建て、容積建て、従価建て、個数の4本建て
17 高価品約款とは 70
輸送者の責任限度額を超える高価品の運送では、割増運賃が必要に
第4章 モノを運ぶ「通関・船積・荷卸し」のしくみ
1 税関とはどういうものか 74
輸出入貨物や旅客等、あらゆるものの国境通過の管理・取締りを行なう
2 関税とはどういうものか 75
輸入品に課される税金で、品目毎に関税率が定められている
3 申告納税制度とは 76
関税の納付は、申告者(輸入者)による適正な手続きを前提にしている
4 一般特恵関税とは 77
特定の発展途上国からの輸入品には、割安の税率が適用されることも
5 保税制度とはどういうものか 78
定められた保税地域では、関税の支払いが一時的に留保される
6 通関業者とその役割 79
通称“乙仲”とよばれ、輸出入貨物の通関を専門的に行なう
7 輸出通関の手続き 80
貨物を保税地域に搬入後、検査を受けるとともに輸出申告を行なう
8 輸入通関の手続き 81
貨物の到着→保税地域への搬入→輸入審査→関税支払いの手続き
9 海上輸送の流れと手続き① 82
貨物の用意とともに、輸出者は船腹の予約を行なう
10 海上輸送の流れと手続き② 83
通関や船積の手続きは、通常は乙仲等の専門業者が代行する
11 検量、検数とは何か 84
許可を受けた業者によって、貨物の数量や状態の検査を受ける
12 輸入貨物の荷卸し 85
通常、通関業者が積卸しから通関、搬送までの一貫作業を行なう
13 船荷証券(B/L)の流れとは 86
本船への船積・出航後に発行され、裏書により発効する。譲渡も可能
14 航空輸送の流れと手続き 87
航空会社と直接契約を結ぶほか、混載業者に委託する場合もある
15 コンテナ輸送のしくみ 88
荷役や運行を簡便化し、ドア・ツー・ドアの一貫輸送を実現
16 複合輸送とは何か 89
船舶と鉄道等、いくつかの運送手段を組み合わせた一貫輸送のこと
17 L/G引取りとは 90
書類が遅れて貨物が引き取れないときの慣行
第5章 「代金決済」と「船積書類」のしくみ
1 信用状決済の当事者と書類(カミ)の流れ 94
荷為替手形が輸出者から買取銀行、発行銀行、輸入者の順に流れる
2 信用状の支払確約文言とは 95
一見難しそうな文面も、書かれている項目は共通している
3 信用状統一規則とは 96
国際ルールによって、異なる商習慣を越えた取引の円滑化を図る
4 船積書類とはどういうものか 97
通常はB/L、保険証券、インボイス、パッキング・リストの4点セット
5 B/L、AWBの特質と役割とは 98
B/Lは有価証券であり、紛失すると貨物を引き取れない場合もある
6 B/Lの種類 99
貨物に事故がなく、船積を確認した船積済B/Lでなければならない
7 荷為替手形と船積書類 100
為替手形に船積書類を添付した荷為替手形で、決済が行なわれる
8 信用状取引の留意点① 101
信用状を受け取った輸出者は、直ちに契約条件と相違ないかをチェック
9 信用状取引の留意点② 102
船積後、輸出者は船積書類と信用状条件の整合性をチェックする
10 厳密一致の原則とディスクレ 103
信用状条件と少しでも違いがあると、買取を断わられる場合もある
11 ディスクレがあるときの対処法とは 104
最も望ましいアメンド依頼。場合によってはL/G等の方法もある
12 輸入信用状はどう開設するか 105
銀行に信用状を依頼するには、十分な担保の差入れが必要に
13 信用状によらない取引とは 106
為替手形を伴わない送金や、為替手形を伴うD/P、D/A等がある
14 送金ベースの決済のしくみ 107
為替銀行を通じて、電信、郵送、小切手等の方法で代金を送金する
15 D/P、D/A決済とはどういうものか 108
輸入者の、荷為替手形の支払いまたは引受けと引替えに決済が完了
16 D/P、D/A手形の買取と取立 109
信用状が付かないので、手形保険の有無と輸入者の信用度による
COLUMN アジアリスク『海賊の襲撃』 110
第6章 「貿易保険」「海上保険」とはどういうものか
1 貿易保険とは何か 114
非常危険と信用危険、為替リスクをカバーする保険
2 貿易一般保険とは① 115
貿易一般保険には、普通輸出保険、輸出代金保険、仲介貿易保険がある
3 貿易一般保険とは② 116
対象契約の非常危険と信用危険がカバーされる
4 貿易一般保険とは③ 117
貿易一般保険の契約の結び方、保険料の計算方法
5 前払輸入保険とは 118
代金を前払い後、相手が商品を送れなくなった場合を想定した保険
6 輸出手形保険とは 119
為替銀行が輸入者の手形不渡りの危険をカバーするための保険
7 海外商社名簿とバイヤーの格付け 120
貿易保険の申込みでは、相手先がこの名簿に登録されていることが必要
8 海上保険、航空保険とは 121
貨物の輸送途上での危険をカバーするもので、古い歴史をもつ
9 海上(航空)保険の申込手続き 122
保険会社に対する告知義務を怠れば、保険会社は責任を免れることも
10 協会貨物約款とは何か 123
ロンドン保険業者協会作成の共通フォームで、旧約款と新約款がある
11 オールリスク担保とは 124
幅広い危険をカバーするものの、戦争やストライキ等は除外される
12 予定保険とはどういうものか 125
輸送や対象物を特定しなくても、保険をかけることが可能
13 共同海損とは何か 126
貨物の全滅を防ぐための一部の損失は、利害関係者で公平に分担する
14 保険求償の手続き 127
損害が起こった場合には、何よりも速やかな手続きが求められる
15 輸出FOB保険とは 128
輸出契約における国内の運送範囲には、輸出FOB保険が必要になることも
第7章 「外国為替」と「貿易金融」の基本
1 外国為替とは何か 132
国際取引では、銀行が介在してお金の移動を伴わず決済が行なわれる
2 外国為替相場とは 133
一国の通貨と他の国の通貨との交換比率を外国為替相場という
3 外国為替市場とは 134
世界中で、24時間休むことなく取引が行なわれるグローバル市場
4 外国為替取引の自由化 135
自由化により、国内の外貨決済や海外での相殺取引も可能に
5 顧客市場とインターバンク市場 136
外為市場は銀行間の市場と、企業や個人と銀行との市場に分かれる
6 外国為替の売買レートのいろいろ 137
ひと口に外為レートといっても、いくつかの種類がある
7 外国為替の先物予約とは 138
貿易取引では、為替変動リスクを避けるため先物予約を行なう
8 スワップ取引とは何か 139
受渡し日の異なる同額の直物と先物、先物と先物の反対売買を行なう
9 為替相場の変動と輸出入取引 140
為替差損を出さないためには、円建て取引や先物予約の方法をとる
10 ネッティング(相殺決済)とは 141
多角的ネッティングは資金効率向上と為替リスク管理の手段
11 貿易金融とはどういうものか 142
輸出入取引を円滑にするための金融と、現地金融とに大別される
12 輸出金融とは 143
輸出者への金融で、取引の段階によって3種類に分かれる
13 輸入金融とは 144
輸入者に運賃や決済資金を融資したり、代金支払いの猶予を行なう
14 国際協力銀行とその役割 145
企業への各種金融のほか、出資や発展途上国への援助も行なっている
15 基軸通貨と各国の為替相場制度 146
変動相場制から固定相場制・中間的制度と多様化している
第8章 「貿易クレーム処理」と「特殊な貿易取引」
1 クレームの原因と対策とは 150
品質保証責任を重視し、クレーム対応力を強化する
2 クレーム処理の手続き 151
クレームが発生したら、直ちに3つの相手に通知する
3 商事仲裁とは何か 152
両当事者および仲裁人による私的裁判で、国によって方法は異なる
4 仲裁判断の効力とは 153
仲裁はあくまで両者の合意が原則。仲裁判断には強制力がある
5 仲裁制度のメリット、デメリットとは 154
拘束力をもつだけに、仲裁人の選定が一番のカギになる
6 ICCによる調停と仲裁とは 155
国際商業会議所の仲裁では、国際商慣習や取引慣行の重視が特徴
7 特殊貿易とはどういうものか 156
承認を要する委託加工貿易と、原則自由の委託販売貿易がある
8 仲介貿易とは 157
書類上は仲介者が輸入し再輸出するが、貨物は第三国間で直送
9 プラント輸出とは 158
生産設備や大型機械の輸出のこと。通常は、設備のほか技術移転も伴う
10 L/Gとは 159
銀行保証状は、プラント輸出のリスク管理の有力手段
11 不可抗力とは何か 160
あらゆる事態を想定し、契約不履行時の免責内容をよく詰めておく
12 並行輸入とその管理 161
真正商品の並行輸入は、誰でも自由に行なえるよう指導されている
13 製造物責任とはどういうものか 162
米国では、たとえ無過失でも多額の賠償責任を負うことがある
14 “RoHS”、“REACH”とは 163
EU向け輸出企業の重要課題となる有害物質規制
15 貿易手続きの電子化とは 164
貿易の事務手続きが電子化され、手続きの時間が短縮される
16 “技術”の取引も貿易のひとつ 165
技術の導入・輸出に伴うロイヤルティの収支も、近年は黒字が拡大
17 自由貿易を推進するWTOの役割 166
関税引下げと自由貿易を推進する国際機関
さくいん 167
著者プロフィール
稲葉英幸
1967年、東大卒。宇部興産、住友ビジネスコンサルティング国際部を経て独立、株式会社東京国際研究所を設立、所長。国際経営、国際取引全般のコンサルティング、海外ビジネス支援、セミナー講師等を幅広く行なう。著書に『海外ビジネスのすすめ方』(当社)、『国際取引入門講座』(総合法令)など。