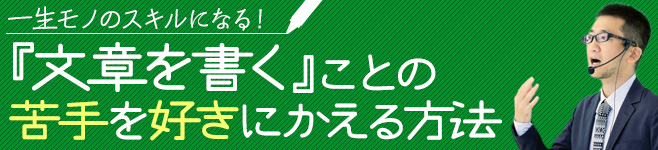一生モノのスキルになる!
『文章を書く』ことの苦手を好きにかえる方法 <連載第91回>
伝える力【話す・書く】研究所を主宰し、「文章の書き方」に精通する山口拓朗さんに書き方のコツを教わります。今回は「冒頭の一文」について。
読まれる文章には「仕掛け」がある
情報があふれるこの時代、文章は「書く」ことよりも、「読んでもらう」ことのほうが難しくなってきました。たとえばSNS。時間をかけて投稿した文章も、その多くは、あっという間にタイムラインに埋もれ、誰の目にも留まらず消えていく。あなたの文章もそのひとつになっていませんか。
一方で、その投稿を読むつもりなどなかったのに……なぜか引き付けられ、気がつけば読み進めていた。そんな経験をしたことのある人もいるでしょう。実は、そうした文章には、ある仕掛けが隠されています。読者の注意を引き、引き込み、離さない。本稿では、その仕掛け「滑り台効果」についてご紹介します。
「滑り台効果」とは何か?
精読率や反応率の高い文章には、「滑り台効果」と呼べる力が働いています。滑り台とうのは、一度滑り出すと、途中で止まることができません。文章も同じです。出だしでしっかり興味をつかむことができれば、読者はその勢いでスルスルと読み進めてくれるのです。
反対に、冒頭で心をつかめなければ、どんなに中身が良くても、続きを読まれる確率は下がります。時間をかけて書いた文章も、そのほとんどが読まれない。書き手にとって、これほど悲しいことはありません。
カギを握るのは「第1センテンス」
この“滑り出し”を演出するうえで最も重要なのが、冒頭の一文、すなわち「第1センテンス」です。アメリカの伝説的コピーライター、ジョセフ・シュガーマンはこう語っています。「第1センテンスの唯一の目的は、第2センテンスを読ませることである」と。まさに至言。文章とは、一文一文が、次の一文を読ませるために存在していると考えることができます。とりわけ、最初の一文で読む人の興味を引けるかどうかで、その文章の運命は大きく変わります。
シンプルな2つの基本ルール
では、読者の興味を引く第1センテンスとはどのようなものか? ポイントはたった2つ。「短いこと」と「興味を引くこと」です。具体例を見てみましょう。
【悪い書き出し(例)】
人は睡眠の質を高めることによって、日々の集中力を高め、メンタルを安定させることができるため、睡眠環境の整備が重要なのです。
|
冒頭から息切れしそうです。内容量も多く、「読むのが面倒」と感じさせてしまう文章です。
【良い書き出し(例)】
そのベッドが、あなたの人生を変えるかもしれません。
|
一転して、こちらは短くて印象的。「どういうこと?」という疑問が湧き、続きを読みたくなります。これが「滑り台効果」を生み出す書き出しです。
「ついうっかり」読み進めてしまう書き出し例
続きを読みたくなる書き出しの例をいくつかご紹介します。
【良い書き出し(例)】
・成功の秘訣? それはルールを破ることです。
・“やる気が出るまで待つ”は、時間の無駄です。
・人生最悪の一日が幕を開けました。
・99%の人が間違えている考え方があります。
・告白します。食い逃げしました。ただし、食べ物の食い逃げではありません。
・その日、私は帰宅すると、すぐにスマホを机の引き出しにしまい、カギをかけました。
|
どれも短く、かつ「共感」「驚き」「問い」「物語性」など、読者の感情を動かす要素が含まれています。読み手の頭に「え?」「なぜ?」「ホントに?」「どういうこと?」という、いい意味での“疑問”を生み出せれば、滑り台効果は自然に発動します。
書き出しは〈最後〉に整える
多くの人は、文章を冒頭から順に書こうとします。しかし筆者のおすすめは、「書き出しは〈最後〉に整える」という発想です。まずは文章全体を書ききって、伝えたい内容や展開が明確になった段階で、改めて最初の一文を見直す。「この文章を読ませるには、どんな書き出しが最も効果的だろうか?」と逆算して考えるのです。
そうすることで、全体の流れにマッチした、インパクトのある導入が生まれやすくなります。結果として、読者の心を一瞬で引き込むことができるのです。書き出しは、単に「文章のスタート」ではありません。その文章を読んでもらえるかどうか、重要な役割を担っています。「書き出しに力を入れる!」で、「読まれない文章」を「読まれる文章」に変えましょう。
山口 拓朗(やまぐち たくろう)
伝える力【話す・書く】研究所所長。山口拓朗ライティングサロン主宰。出版社で編集者・記者を務めたのち、2002年に独立。26年間で3600件以上の取材・執筆歴を誇る。現在は執筆活動に加え、講演や研修を通じて、「1を聞いて10を知る理解力の育て方」「好意と信頼を獲得する伝え方の技術」「伝わる文章の書き方」などの実践的ノウハウを提供。著書に『読解力は最強の知性である 1%の本質を一瞬でつかむ技術』(SBクリエイティブ)、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』(ダイヤモンド社)、『マネするだけで「文章がうまい」と思われる言葉を1冊にまとめてみた。』(すばる舎)、『1%の本質を最速でつかむ「理解力」』『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』『何を書けばいいかわからない人のための「うまく」「はやく」書ける文章術』(以上、日本実業出版社)、『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』(明日香出版社)、『ファンが増える!文章術——「らしさ」を発信して人生を動かす』(廣済堂出版)ほか多数。