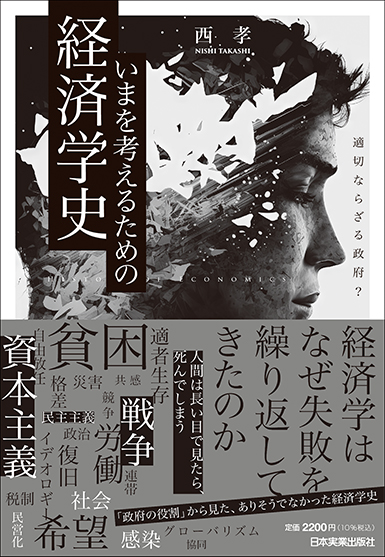「経済学は厳密な意味での科学ではない」──杏林大学の西孝(にし たかし)教授は著書『いまを考えるための経済学史 適切ならざる政府?』でそう述べています。そして、だからこそ経済学の歴史である「経済学史」を学ぶべきである、とも。経済学はなぜ科学とは言えないのか、また過去の経済学者の理論や思想を学ぶことにどんな意味があるのか。同書の「はじめに」を抜粋して掲載します。
物理学の学生はニュートンを読むか?
いきなりで恐縮ですが、経済学史は、いったい何のために勉強するのだと思いますか?私の答えは、「いまを理解するため」というものです。そしてそういう答えになる理由は、「経済学は厳密な意味での科学ではない」からであると考えています。この点は、本書の目指すところとおおいに関わりがあるので、まずはそこから説明しましょう。
そもそも読者のみなさんにとって経済学のイメージってどんなものでしょうか? ミクロとかマクロとか、数式がいっぱい出てくるとか、高価な統計ソフトを使ってデータ分析を行なうとか……。まるで、理系の科目のようだと思っている人も多いのではないでしょうか。
でもそれなら、理系の勉強をする人は、過去の学説史を読むでしょうか?物理学を学ぶ人は、ニュートンやガリレオの古典を読むでしょうか? 医学の勉強をする人は、ヒポクラテスや杉田玄白の著作を読むでしょうか? おそらく答えは「NO」でしょう。仮に読むとしても、それは教養として、または純粋に歴史的な興味の対象としてであって、目の前の自然現象を説明するためや、目の前の患者を救うためではないでしょう。
でも、それはなぜでしょうか?
自然科学の場合は、基本的に過去にあったさまざまな考察や理論に一応の決着をつけ、それらを包摂する形で現在に至っていると考えることができるのです。それが可能なのは、制御された形での厳密な実験を行なうことができて、それによって仮説を検証・反証することが原則として可能だからです。私が「厳密な意味での科学」と言っているのはそういうものを指しています。いわば、対立する仮説に白黒をつけて前に進むことができるわけです。
もちろん、100%というわけにはいかないし、分野によって程度の差もおおいにあるでしょう。でも、地動説か天動説かで、いま論争になることはないし、金(gold)を作るために何と何を混ぜるかなんていう錬金術の方法が諸説乱立することもありません。最新の教科書を読めば、そこに必要なものがほぼ含まれていると言っていいわけです。
経済学は厳密な意味での科学か?
では、同じことは経済学にも当てはまるでしょうか? 経済学者の中には、経済学はまさにそのような意味で「科学的」なのだと信じている人も少なくありません。
しかし、もし本当にそうなら、経済学においても、現代の教科書を読めば用は足りるのであって、過去の古典を読む必要はないことになります。それは教養のためか、せいぜい純粋に歴史的興味の対象でしかあり得ないはずです。
実は、私が学生時代に習った経済学史はまさにそんな感じだったのです。現代の一般均衡理論を核とする経済理論──それは新古典派経済学と呼ばれています──は、一つの完成型、到達点であると考えられているのです。したがって、経済学史というのは、そこにたどり着く過程に現れた、さまざまな点で現在よりも「未熟な」経済学を学ぶためにあるというわけです。過去の経済学者が取り上げられて賞賛されるのは、現代の理論の萌芽となる考え方が、いつ頃から現れたのかを見るために過ぎないのでした。
しかし私の、そして本書の立場はそうではありません。簡単に言うと、経済学はいま述べたような意味での厳密な科学では決してありません。しかし、まさにそれだからこそ、過去の理論を勉強するべき理由があるのです。
まず、経済現象に関する限り、制御された実験を行なう余地はきわめて限られています。問題となっている側面以外は、すべての点で同じであるような二つの経済を作り上げて、片方の経済についてだけある政策を行なう、などということは決してできません。数学を用いたモデルも、複雑な経済現象を著しく単純化することで成立しているのであって、それをもって一般的・普遍的な法則を確立することはできないのです。
それだけではありません。時代とともに社会も経済も変化します。そうだとすれば、社会や経済を支配するメカニズムも変化し続けていると考えるのが自然です。物体の落下法則は、ガリレオやニュートンの時代も現在と同じだと考えていいでしょう。しかし、社会や経済の仕組み・制度や人間の振る舞いは、時代を通じて同じではないのです。いや同じ時代であっても、国によって、地域によってそれらが異なっていると考えるべき理由があります。とりわけ、経済開発や経済危機への対応という文脈で、これまで経済学は、一つの経済政策をあらゆる国に自信満々に適用して失敗してきたのだと思います。
私のそういった物言いに反対する経済学者もいるでしょう。ただ、これまであった数々の論争に対して、常にきっちりと科学的に白黒をつけて今日があるわけではないことは、誰もが認めざるを得ないのではないでしょうか。経済問題については、これまでも現在も、さまざまな意見の不一致が存在し、さまざまな論争が行なわれてきました。経済学が実証分析に基づいて、それらにちゃんと決着をつけたことは決してないのです。それどころか、実質的に同じ内容の論争が何度も繰り返されていることも珍しくありません。
理由は簡単です。誰もが納得せざるを得ない方法で制御された実験を通じて、物事に決着をつけることがそもそもできないのですから。そしてそうであるとすれば、いまある新古典派経済学は、過去のすべてに白黒の決着をつけた上で存在しているわけではなく、逆に、それ以外のさまざまな理論や学説を排除して、置き忘れて、無視してきた結果として、あるいはさまざまな偶然の結果として存在していることになります。
現在支配的となっている経済理論や政策は、正しいから生き残ったとは限らないのです。その時その時の、一番有力な力によってご贔屓にされたものが生き残ったというだけかも知れません。流行などという言葉は使いたくありませんが、残念ながら、経済学にもそれはあるのです。いや、確かにあったのです。
「である」と「であるべき」の違い
もう一つ強調しなければならない点として、経済学の論争は、その少なからぬ部分が、経済政策をめぐって行なわれるということです。そこには多くの場合、必ず「価値判断」が関与します。つまり、物事が「どうあるか」だけではなく、「どうあるべきか」を議論することが不可欠なのです。太陽が東西どちらから昇る「べき」か、重いものと軽いものはちらが先に落ちる「べき」か、なんて議論が自然科学でなされることはないでしょう。しかし経済学では、ある政策によって、Aという状態がBという状態に変化するとき、さて、それはどちらが「良い」状態なのかを判断することなしに、政策の優劣を論ずることはできません。それはまさに価値判断に関わるのです。
読者のみなさんは、そのような価値判断を抜きに、客観的に白黒をつけられる社会経済現象がどれほどあると思いますか? それがたくさんあるのだ、そして経済学はそれに対して中立的・客観的な答えを提供できるのだ、と誤解してきたことが、今日の経済学の役立たずぶりをもたらしている、と私は思っているのです。みなさんもそう思いませんか?
このあと本書で見るように、科学的客観性を標榜してきた経済学は、実は、自然法思想とか功利主義とか、特定の価値判断をその中に嫌というほど含んでいるのです。
私の考えでは、経済学は自然科学よりは、道徳哲学、社会思想にはるかに近いものです。もちろん、これまで積み上げられてきた理論的・実証的な分析技術を、決して過小評価するものではありません。しかし、経済学において仮説を検証・反証する能力が著しく限られていることを認めるのであれば、結果として経済学は、さまざまなモデル、さまざまな論考・思想の集まりであることを認めなければならないはずです。そうであれば、過去の経済学もまた、その重要な構成要素の一つなのです。
現在の経済学が置き忘れたもの
われわれが過去の経済学者の主張に耳を傾けるのは、単なる物好きの興味本位でも、教養としてでもなく、まさに現代の問題を考察するための「材料」としてなのです。そして、ひたむきに事実を分析する一方で、その情報に基づいて物事にどのように対処するのかを議論するときには、進んで価値判断に関わるべきだと思っているのです。過去の経済学は、そのための素材も提供してくれます。
過去の経済学者の論考について、おそらく現代の洗練された経済学者たちは、そのモデルの前提が明確ではない、さまざまな因果関係に関する論理的推論が厳密ではない、あるいはそもそも閉じたモデルにすらなっていない等々の理由で糾弾することでしょう。しかし他方で、現代の経済理論による高度に洗練された分析手法は、われわれに相応の現実認識の洗練をもたらしているでしょうか?
AV機器がいかにデジタルで高精度なものになろうと、それを見聞きしているわれわれは、相変わらず光の反射や空気の振動をアナログ的に受け取って認知しているのです。錯覚を利用して書かれた絵画を見て「まるで本物のようだ」と称賛する一方で、本物の美しい景色を見た時には「まるで絵のようだ」と言う。それが人間のアナログ感覚というものではないでしょうか。いかに厳密な数学的推論で処理され、いかに大量のデータを高度な統計的手法で分析したとしても、そこから何かを受け止め、現実社会への政策的適用を判断するのは、アナログ仕様の政治的、思想的、倫理的価値判断であり続けていることを忘れるべきではありません。
今日ほど洗練も抽象化もされていない過去の経済論考は、しかしそのすぐれて総合的な視点ゆえに、現代の経済学が置き忘れ、放置し、無視し、覆い隠しているものへの洞察に満ちていると思います。それらはもう一度拾い直されねばならず、その意味で経済学史を学ぶことは、単なる教養ではなく、まさに現代の問題を考えるために重要な作業なのだと思うのです。
著者プロフィール
西孝(にし たかし)
杏林大学総合政策学部教授。1961年東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。専攻は、マクロ経済学、国際金融論。著書に『イントロダクション マクロ経済学講義』(日本評論社)、『社会を読む文法としての経済学』(日本実業出版社)ほか。