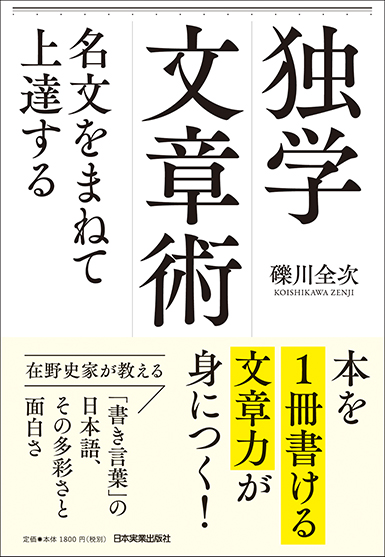在野の歴史研究家として、『独学で歴史家になる方法』(小社刊)など多くの著書を持つ礫川全次(こいしかわぜんじ)氏。最新刊『独学文章術』では、「文章上達の極意は名文をまねること」というスタンスから、明治の近代口語文草創期の福沢諭吉、夏目漱石や現代を代表する書き手、村上春樹までのそうそうたる歴史的名文家に加え、父の復員を待ちわびる終戦直後の小学生の手紙、話し家の話芸の文章化や映画監督のエッセイなどにいたる多彩な「名文・迷文」を取り上げ、その文体の核をなす論理や息づかいを読み解きます。
同書は全28講からなり、各講で名文を取り上げて解説、さらに演習と設問によって理解を深める、という構成です。その中から2講を選び、公開します。
ふたつめは第19講、テーマは「村上春樹と『猫』のメタファー」です。2009年、海外の文学賞受賞で話題になった、村上春樹氏のエルサレムでのスピーチとエッセイを取り上げます。
※数字表記など一部再編集しています。
『独学文章術 名文をまねて上達する』(礫川全次・著)より
第19講 「壁と卵」のメタファー
作家の村上春樹さんは、2009年に、エルサレム賞を受賞しました。村上さんが、この賞の受賞に応じたことは、当時、大きな話題になりました。エルサレム市での授賞式の際に、村上さんがおこなったスピーチの内容も、かなり話題になりました。
最近になって、村上さんの『雑文集』(新潮社、2011年1月)を入手し、その中の“「壁と卵」──エルサレム賞・受賞のあいさつ”という文章を読みました。そこには、さまざまなメッセージが織り込まれていました。これを、順を追って整理しますと、次のようになります。
1 小説家というのは、うまいウソをつくことを職業にしている者である。本当のように見える虚構を創り出すことによって、真実を引っ張り出し、それに光を当てる職業である。
2 ただし、このあいさつでは、嘘をつくつもりはない。
3 この賞を受賞することについて反対する人もあったが、反対されると、かえって賞を受けたいと思うようになった。
4 大きな壁と、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立つ。これは、ひとつのメタファーである。
5 私が小説を書く理由は、個人の魂の尊厳を浮かび上がらせ、そこに光を当てるためである。
6 私の父は、昨年〔2008〕の夏に、90歳で亡くなった。子供のころの父は、戦地で死んでいった人のために、毎朝、深い祈りを捧げていた。
7 我々には生きた魂があるが、システムには魂がない。システムに我々を利用させてはならない。
このうち「5」、あるいは「7」は、あとの【設問19】と関わってきます。ここで少し、原文を引いておきます。
私が小説を書く理由は、煎じ詰めればただひとつです。個人の魂の尊厳を浮かび上がらせ、そこに光を当てるためです。我々の魂がシステムに絡めとられ、貶められることのないように、常にそこに光を当て、警鐘を鳴らす、それこそが物語の役目です。私はそう信じています。〈79ページ〉
村上さんは、「4」で、メタファーという言葉を使っています。メタファー(英語ではmetaphor)は、一般に「暗喩」と訳されています。「4」でいう「壁と卵」は、ひとつのメタファーであり、それは、「5」や「7」の内容を示唆しているように読めます。
いずれにしても、この「受賞のあいさつ」は、村上文学の本質を探ろうとしている者に、重要なヒントを提供しているようです。その際のキーワードは、虚構とメタファーです。
村上さんとその父親
村上さんは、その後、雑誌『文藝春秋』の2019年6月号に、「猫を棄てる──父親について語るときに僕の語ること」というエッセイを発表しました。
このエッセイは、同号の240ページから始まり、267ページで終わっています。240ページは、その全ページを使って一枚の写真が紹介されています。広場のようなところで、バットを持って投球を待っている半ズボンの少年がいます。その後ろには、グローブをはめてキャッチャーのように構えている中年の男性。この少年が、若き日の村上春樹さんで、中年の男性が、その父親です。村上少年は、素足に木のサンダル、父親は下駄を履いています。
ページ右上に「特別寄稿 自らのルーツを初めて綴った」とあり、右下に「村上春樹」とあります。さらにその下に、村上春樹氏の近影。
この「自らのルーツ」という言葉は、たしか、新聞広告にも載っていたと記憶します。この言葉に反応し、同誌同号を買い求めた人は、少なくなかったでしょう。かく言う私も、その一人です。
エッセイは、全部で14の節に分かれています。最初の節は、「父親と村上少年と猫」の話です。最後の節に、もういちど「猫」が出てきます。その間の12節は、ほとんど「父親」の話です。父親の生い立ちの話、父親と兵役についての話、あるいは父親と村上さんの関係についての話です。
村上さんは、なぜここで、自分の「父親」について語ったのでしょうか。エッセイの250ページによりますと、村上さんは、父親の死後5年が経ってから、その軍歴を調べてみようと思い立ったそうです。父親が亡くなったのが2008年ですから、2013年ころから調べはじめたのでしょう。調査の過程で、父親が「南京攻略戦」に参加していなかったことが判明します。「ひとつ重しが取れたような感覚があった」と、村上さんは書いています。
そうした軍歴調査が、今回のエッセイに結びついたことは、間違いありません。しかし、それ以上に大きいのは、村上さん自身が「老境」を意識されたことではないのでしょうか。村上さんは、このエッセイを書かれた時点で、70歳です。吉川英治、江戸川乱歩、吉行淳之介といった作家は、70歳で亡くなっています。橋本治さんも、2019年1月に、70歳で亡くなっています。
かつては、父親のことを「老人」として意識していた村上さんですが、気づいてみると、自身が「老境」に達していました。──そうした中で、改めて、自分の「父親」について振り返ったのが、このエッセイだったのではないでしょうか。
棄てた猫が戻ってくる
それにしても、自分の父親をテーマにしたエッセイに、なぜ、「猫を棄てる」というタイトルが付いているのでしょうか。
このエッセイは、小学校の低学年だった村上さんが、父親とふたりで、一匹のメス猫を海辺まで捨てにいくエピソードから始まっています。昭和30年代初めのことだったようです。ところが、猫を捨てて帰ってくると、すでに猫は家に戻っていて、玄関で、「にゃあ」とふたりを迎えたそうです。
この話は、実際にあった話だと思いますが(ウソではないと思いますが)、同時に、「メタファー」だと思います。村上さんの父親は、京都のお寺の次男に生まれましたが、子どものころ、「口減らし」のために、奈良の寺に預けられたことがありました。しかし、「寒さのために健康を害し」、実家に戻されます。捨てたはずの猫が戻ってくるというメタファーは、父親が子ども時代に体験した苦労として解釈できるように思います。
さらに、このメタファーについては、もうひとつ、別の解釈も可能です。エッセイによれば、村上さんは、職業作家になったころから、父親とは、ほとんど絶縁状態にあったようです。村上さんは、しかし、父親が90歳を迎えたころ、入院中の父親を訪ね、「和解のようなこと」をおこないました(264~265ページ)。父親が村上さんを捨てたのか、村上さんが父親を捨てたのか、双方が互いに相手を捨てたのか。このあたりは、よくわかりません。しかし、捨てたはずの猫が戻ってくるというメタファーは、この和解という出来事としても解釈できると思いました。
木から降りられなくなった猫
このエッセイの最後の節にある見出しは、「松の木を上っていった猫」です。そこで村上さんは、再び猫の思い出を語っています。子ども時代に出会った猫ですが、最初の節に出てくる猫とは別の猫です。
その猫は、白い可愛い子猫でした。その子猫は、ある日、村上少年が見ている前で、庭にあった松の木をスルスルと登っていきました。しかし、あまりに高いところまで登ったので、降りられなくなってしまいました。その子猫が、その後、どうなったかはわかりません。松の枝に「しがみついたまま、死んでひからびてしまった」のかもしれません。少なくとも、村上少年は、松の木を見上げながら、そのように想像しました。「降りることは、上がることよりずっとむずかしい」──これは、松の木から降りられなくなった子猫を見て、少年時代の村上さんが、心に刻んだ教訓です。
この話を紹介するにあたって、村上さんは、次のように述べています。
もうひとつ子供時代の、猫にまつわる思い出がある。これは前にどこかの小説に、エピソードとして書いた記憶があるのだが、もう一度書く。今度はひとつの事実として。
わざわざ、「ひとつの事実」と断っています。しかし、この言葉を信じてはなりません。小説家は、うまいウソをつくことを職業にしていますから。
この「木から降りられなくなった猫」という話もまた、メタファーだと思います。では、このメタファーが暗示しているものは、いったい、どういうことなのでしょうか。
わたしは、次のように捉えました。村上春樹さんの文学は、みずからの「根」(ルーツ)にあるものを捨て去ることによって、きわめて高いところまで登りつめました。しかし、「老境」に達したのを機会に、みずからの「根」にあるものを意識します。あるいは、みずからの「根」にあるものと和解しようとします。たとえば、「父親」という存在です。ところが、その「根」にある部分まで降りていく作業が、意外に困難であることに気づきます。
──というわけで、こちらの猫の話も、最初の猫の話と結びついてくるわけです。
さて、ここで設問です。
村上春樹さんのエッセイの最後に、次のような一節があります。これを読んで、あとの3つの小問に答えてください。なお、傍点は、原文のままです。(編集部注:傍点は下線に差し替えています)
言い換えれば我々は、広大な大地に向けて降る膨大な数の雨粒の、名もなき一滴に過ぎない。固有ではあるけれど、交換可能な一滴だ。しかしその一滴の雨水には、一滴の雨水なりの思いがある。一滴の雨水の歴史があり、それを受け継いでいくという一滴の雨水の責務がある。我々はそれを忘れてはならないだろう。たとえそれがどこかにあっさりと吸い込まれ、個体としての輪郭を失い、集合的な何かに置き換えられて消えていくのだとしても。
小問1 文中の「一滴の雨水」に対応する言葉を、「エルサレム賞・受賞のあいさつ」から選ぶとすれば、それは何でしょうか。
小問2 文中の「集合的な何か」に対応する言葉を、「エルサレム賞・受賞のあいさつ」から選ぶとすれば、それは何でしょうか。
小問3 村上さんは、「受け継いでいく」という七文字に、わざわざ傍点を施しています。その理由を推定してください。
小問1解答
個人の魂
小問2解答
システム
小問1・2解説
「卵」や「一滴の雨水」は、個人の魂のメタファーであり、「壁」や「集合的な何か」は、システムのメタファーです。したがって、小問1の解答は「卵」でもよく、小問2の解答は「壁」でもよいでしょう。
小問3解答例
個人の魂は、別の個人の魂へという形で受け継がれていくべきだから。
小問3解説
個人の魂は、別の個人の魂へという形で受け継がれていくべきだという発想は、「エルサレム賞・受賞のあいさつ」にはありませんでした。この発想は、その後、父親という「ルーツ」について調べていくうちに、生まれてきたものと考えます。
■第19講まとめ
▼小説家は、本当に見える虚構を創り出すことで、真実を引き出すことができる。
▼村上春樹の小説は、システムに絡めとられがちな個人の魂に光を当てている。
著者プロフィール
礫川全次(こいしかわ ぜんじ)
1949年生まれ。1972年東京教育大学卒業。在野史家。「歴史民俗学研究会」代表。フィールドは近現代史、犯罪民俗学、宗教社会学。著書:『独学で歴史家になる方法』(小社)、『史疑 幻の家康論』『戦後ニッポン犯罪史』『大津事件と明治天皇』『サンカ学入門』『攘夷と憂国』『独学の冒険』『雑学の冒険』(以上、批評社)、『サンカと三角寛』『知られざる福沢諭吉』『アウトローの近代史』『日本人はいつから働きすぎになったのか』『日本人は本当に無宗教なのか』(以上、平凡社新書)他多数。