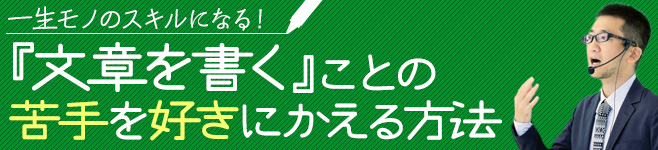一生モノのスキルになる!
『文章を書く』ことの苦手を好きにかえる方法 <連載第86回>
伝える力【話す・書く】研究所を主宰し、「文章の書き方」に精通する山口拓朗さんに書き方のコツを教わります。今回は「伝わる文章」について。
伝わらない原因はどこにある?
「メールや企画書を書いても、なかなか意図が伝わらない」「せっかく丁寧に書いたのに、なぜか伝わらない」——そんな“モヤモヤ”を抱えているビジネスパーソンは少なくありません。その原因のひとつに、言葉の“抽象度”をマネジメントできていない点が挙げられます。
わかりやすく説得力のあるビジネス文書を書くためには、「抽象」と「具体」を行き来する意識が不可欠です。抽象とは「概念的で広く捉えられる表現」のことで、具体とは「数字・事例・描写などを使って、誰もが同じようにイメージできる表現」のこと。両者を適切に組み合わせることで、読み手の理解と納得が大きく変わります。
最初は「抽象→具体」の流れをつくってみる
まず、抽象表現だけで書かれた文章を見てみましょう。
【文例(1)】
このテストプロジェクトは顧客満足度の向上に大きく貢献しました。
|
一見、ポジティブな報告のようですが、読み手は「具体的にどう貢献したのか?」がわからず、納得感を得られません。ここに具体的な成果を添えることで、説得力が一気に高まります。
【文例(1)の改善例】
このテストプロジェクトは顧客満足度の向上に大きく貢献しました。具体的には、問い合わせ対応時間が平均30分から10分に短縮され、顧客アンケートの満足度スコアが72点から89点に上昇しました。
|
このように、「抽象→具体」の流れをつくることで、読み手の反応は大きく変わります。特に上司やクライアントなど決裁権を持つ相手に対しては、抽象的な結論に具体的な根拠を添えることで、納得感が格段に高まります。
結論を印象づけるなら“逆の流れ”も効果的
逆に、「具体→抽象」の順で構成するパターンが有効なケースもあります。以下は、ある社員が提案書の冒頭に書いた一文です。
【文例(2)】
現在、当社の営業チームでは、見積書作成に平均して1件あたり約40分を要しています。各担当がExcelを個別管理しており、テンプレートの統一もされていません。そのため、ミスや遅延が頻発しています。こうした状況を改善するには、“営業業務の標準化”が必要です。
|
最初に具体的な現状を提示し、最後に抽象的なキーワード(=提案の方向性)でまとめています。このように、「具体→抽象」の流れで伝えることによって、結論を読み手の記憶と印象に強く残すことができます。
また、抽象的なキーワード(今回の例では「標準化」)を使うことで、複数の具体策への広がりも持たせることができるのです。
ポイントは「抽象⇔具体」のバランス感覚
ビジネス文書において、抽象と具体のどちらか一方に偏ってしまうと、伝わりにくい文章になります。抽象ばかりだと現実味がなく、具体ばかりだと意図が読み取れない——だからこそ、「抽象⇔具体」の往復運動が必要なのです。
企画書でも報告書でも、メールでもプレゼンでも、この2つの視点を取り入れるだけで、相手の理解度と納得度が格段に増します。「今、自分の文章は抽象に寄りすぎていないか? 具体に偏りすぎていないか?」。自身に対して、問いや疑いを持ちながら書くことも重要。「抽象⇔具体」の行き来を意識するだけで、あなたの文章は確実に伝わりやすくなります。
次に書くメールや報告書から、ぜひ試してみてください。。
山口 拓朗(やまぐち たくろう)
伝える力【話す・書く】研究所所長。山口拓朗ライティングサロン主宰。出版社で編集者・記者を務めたのち、2002年に独立。26年間で3600件以上の取材・執筆歴を誇る。現在は執筆活動に加え、講演や研修を通じて、「1を聞いて10を知る理解力の育て方」「好意と信頼を獲得する伝え方の技術」「伝わる文章の書き方」などの実践的ノウハウを提供。著書に『読解力は最強の知性である 1%の本質を一瞬でつかむ技術』(SBクリエイティブ)、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』(ダイヤモンド社)、『マネするだけで「文章がうまい」と思われる言葉を1冊にまとめてみた。』(すばる舎)、『1%の本質を最速でつかむ「理解力」』『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』『何を書けばいいかわからない人のための「うまく」「はやく」書ける文章術』(以上、日本実業出版社)、『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』(明日香出版社)、『ファンが増える!文章術——「らしさ」を発信して人生を動かす』(廣済堂出版)ほか多数。